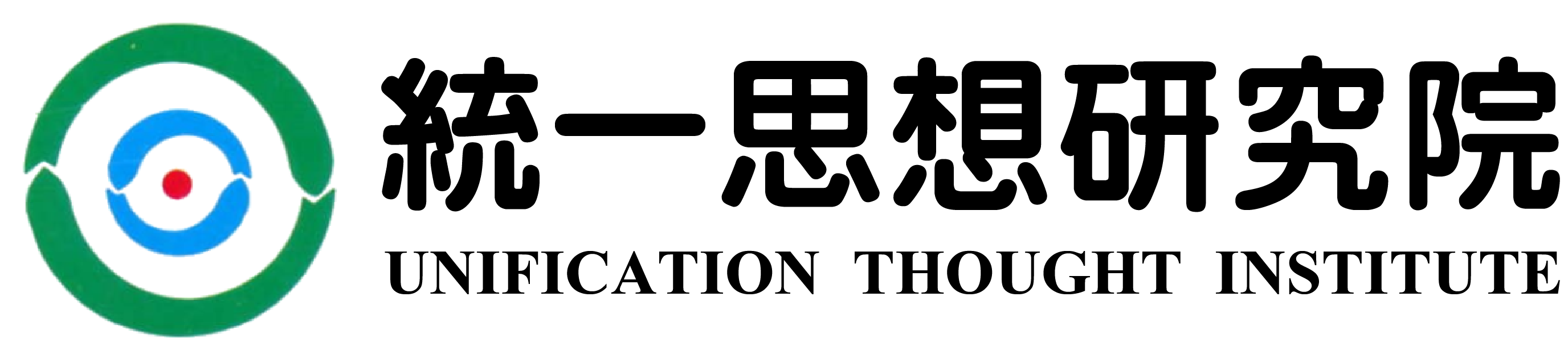第三章 本性論
本性論は人間の本来の姿、すなわち堕落していない本性的人間を扱う哲学部門である。原相論と存在論において述べたように、人類は長い歴史の期間を通じて、人生と宇宙の根本問題を解決するために苦悶してきた。特に今日、共産主義の消滅後の新たな混乱の中で、南北問題、人種紛争、宗教紛争、領土紛争、不正腐敗の拡散、伝統的価値観の崩壊による各種犯罪の蔓延など、数えきれない数多くの問題が、対立と藤、闘争と戦争に結びつきながら、世界は混乱の渦の中に陥っているのである。このような問題は結局、「存在の問題」と「関係の問題」に大別されるのであるが、それはいかにして解決されるのであろうか。
一方、人類歴史の中には、現実の人間の姿に満足しないで、漠然とではあるが、人間の本来的な姿があるだろうという考えから、彼らなりの解答を見いだそうとした人たちがいた。彼らはまさしく宗教家であり、哲学者たちであった。彼らは「人間とは何か」という問題に直面しながら、いかにすれば本来の人間の姿を回復することができるか、その道を追究してきたのである。
紀元前五世紀ごろ、インドのカビラ城に生まれた釈は、修道、苦行の生活を通じて道を悟った。すなわち、人間は本来、仏 性をもっているにもかかわらず、無明によって煩悩に縛られ苦痛に陥るようになったということを悟った。そして人間は修道生活を通じて本性を回復しなければならないと説いた。
イエスも三十余年の生涯において、人生問題を深く探求した結果、人間は罪人であること、そして神の子であるイエスを信ずることによって、再び生まれなければならないと説いた。そしてユダヤの人々に向かって「天国は近づいた。悔い改めよ」と叫んだのである。彼はパレスチナの各地を巡りながら、教えを広めるために全力を尽したが、実権を握っていた当時の政治や宗教の壁を越えることができず、結局、十字架の刑に処せられてしまった。
ソクラテスは当時のポリス社会の末期的な混乱相を直視し、真の知を愛することが人間の真の生き方であると説き、「汝自身を知れ」と叫んだ。プラトンは善のイデアを認識することが最高の生活であるといった。そして、アリストテレスは人間を人間たらしめているのは理性であるが、人間の徳はポリスにおける共同生活において実現されると考え、人間は社会的動物(ポリス的動物)であるといった。ギリシアの哲学者の人間観は、おしなべて人間の本質は理性であり、理性を十分に働かせれば、人間は理想の姿になるというものであった。
中世時代において、キリスト教が西欧社会の人間の精神を支配した。キリスト教の人間観は、人間は罪人であり、イエスを信ずることによって救われるというものであった。そのような立場から見るとき、人間の理性は人間の救いと平和な生活の実現に役立たないと見なされることもあった。ところが近代に至ると、再び人間の理性を重視する思潮が現れた。デカルトは、人間は理性的存在であって、理性でもってのみ正しい知識を得ることができるといい、「われ思う、ゆえにわれあり」(Cogito, ergo sum )という有名な命題を残した。そしてカントは、人間は実践理性の命ずる道徳的義務の声に従う人格的存在であるといい、人間は誘惑や欲望に負けないで理性に従って生きるべきであると説いた。
ヘーゲルも人間を理性的存在であると見た。ヘーゲルによれば、歴史とは理性が世界の中で自らを実現する過程であり、歴史の発展とともに、理性の本質である自由が実現されるのである。そのようなヘーゲルの説によれば、近代国家(理性国家)の成立とともに、人間と世界は合理的な姿になるはずであった。ところが現実において、実際の人間は人間らしさを喪失したままであり、世界は非合理的なままであった。
このようなヘーゲルの極端な理性主義に反対したのがキルケゴールであった。キルケゴールは、世界の発展とともに人間は合理的な存在になるというヘーゲルの主張に反対し、人間は現実社会において、真の人間性を失った平均的人間にすぎないと主張した。したがって、大衆から離れて、単独者として、主体的に人生を切り開くとき、初めて真の人間性が回復されるのである。そのように現実の人間を本性を失った人間としてとらえ、主体的に人間性を取り戻そうとする考え方が、それ以後、実存主義思想として展開された。それに関しては、のちに再び述べることにする。
また、ヘーゲルの理性主義に反対して、人間を感性的人間としてとらえたのがフォイエルバッハであった。フォイエルバッハによると、人間は類的本質である理性、意志、心情(愛)をもつ類的存在であるが、人間はその類的本質を自分から分離して、対象化し、それを神として崇めるようになった。そのようにして人間は人間性を喪失するようになったと見たのであった。したがって、人間が本性(類的本質)を取り戻す道は対象化した神を否定すること、すなわち宗教を否定することによってのみ可能であると主張した。
そしてヘーゲルの自由の実現の思想から出発して、人間の真なる解放を主張したのがマルクスであった。マルクス当時の初期資本主義社会において、労働者の生活は悲惨であった。彼らは長時間の労働を余儀なくされ、しかも最低の生活を維持するのも難しい程度の賃金しかもらえなかった。労働者の間では病気と犯罪が蔓延しており、彼らは人間性を奪われていた。一方、資本家は裕福な生活をしていたが、労働者を無慈悲に搾取し、抑圧しており、彼らも本来の人間性を失っているとマルクスは考えた。人間解放に立ち上がったマルクスは、初め、人間による人間性の回復というフォイエルバッハの人間主義から出発したが、やがて人間は類的存在であるのみならず、生産活動をする社会的、物質的、歴史的存在であり、人間の本質は労働の自由であると考えるようになった。しかるに資本主義社会において、労働者は労働生産物をすべて資本家に奪われており、労働そのものが自分の意志ではなく資本家の意のままになっている。そこに労働者の人間性の喪失があるとマルクスは考えたのである。
労働者を解放するためには、労働者を搾取する資本主義社会を打倒しなくてはならない。そうすることによって資本家もまた人間性を回復するとマルクスは考えたのである。そして彼は、唯物論の立場から、人間の意識を規定しているのは社会の土台である生産関係であると主張し、資本主義の経済体制を暴力的に変革しなくてはならないと結論したのであった。ところが、マルクスの理論に従って革命を起こして成立した共産主義国家は、自由の抑圧と人間性の蹂 躙の甚だしい独裁社会となって、人間はますます本来の姿を喪失してしまった。これはマルクスが人間疎外の原因の把握において、そして人間疎外を解決する方法において、大きな間違いを犯したことを意味しているのである。
ところで、人間の疎外は過去の共産主義社会だけの問題ではない。資本主義社会においても、個人主義と物質中心主義が蔓延し、自分で考えたことはどんなことでもやってもよいという利己的な考え方が広まり、ますます人間性は失われているのである。
人間学がすべての学問と思想の根本であると考えたマックス・シェーラー(Max Scheler, 1874-1928)は、『哲学的世界観』の中の「人間と歴史」において、人間を思考する知性人(homo sapiens)、道具を制作し使用する工作人(homo faber)、そして宗教人(homo religiosus)の三つの類型に分類した。そのほかに人間を経済人(homo economicus )、自由人(homo liberalis)、国家人(homo nationalis)などと見る立場もあった。しかし、それらはいずれも人間の姿をとらえていなかったのである。
このように、人間とは何であり、人生とは何であるかという問題は、人類歴史が始まって以来、数多くの宗教家や哲学者たちによって、その解決が試みられたが、すべてが失敗に終わったのである。そして人生を正しく生きようとしたが人生の真の意味が分からず、虚無な人生を悲観して自殺した人も数多くいるのである。韓国の尹心悳、日本の藤村操などがその代表的な例である。
このような歴史的に未解決の人間の問題を根本的に解決しようとして、その生涯をかけて歩んでこられた方がいらっしゃる。その方がまさに文鮮明先生である。そして文先生は、統一原理において明らかにされたように、人間は、たとえ本来の姿を失って惨めな存在になっているとしても、本来、みな神の子であると宣言されたのである。
人間は神に似せて造られたが、人間始祖の堕落によって、神とは関係のない存在となってしまった。しかし神のみ言に従って生きて、神の愛を受けるようになれば、本来の姿を取り戻すことができるのである。本章では、人間の堕落の問題や人間性の回復の方法について論ずるのではなくて(それに関しては『原理講論』の「堕落論」と「復帰原理」を参照のこと)、ただ本来の人間の姿はいかなるものかを論ずることにする。人間の本来の姿は神相に似た神相的存在であり、神性に似た神性的存在である。そして原相の格位性に似た格位的存在である。次に、これらに関して詳しく論ずることにする。