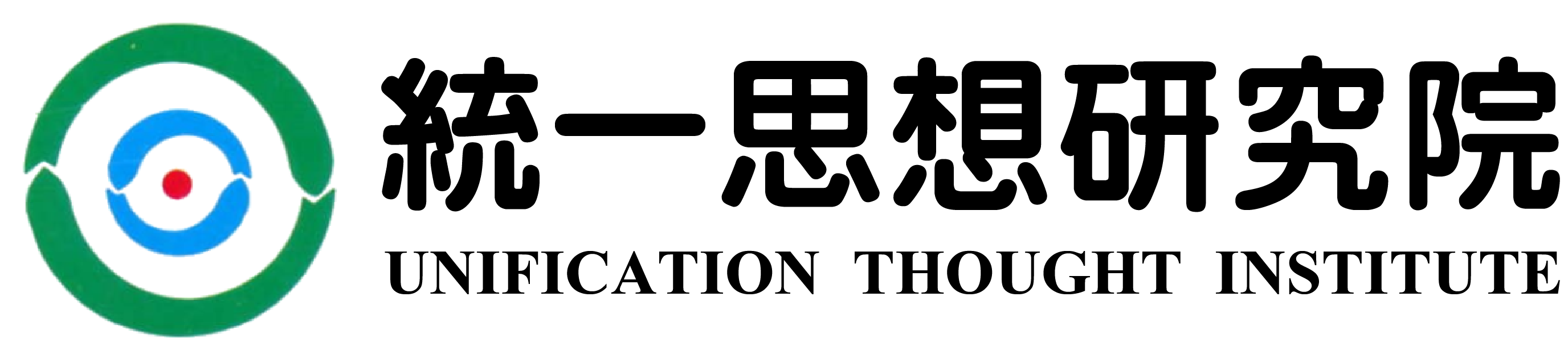(三)個性真理体の個別相
個性真理体は性相と形状、および陽性と陰性の普遍相のほかに、個体ごとに独特な属性をもっている。それが個性真理体の個別相であって、原相の個別相(原個別相)に由来しているのはもちろんである。
普遍相の個別化
個別相は普遍相と別個の属性でなく、普遍相それ自体が特殊化、個別化されたものである。すなわち普遍相は性相と形状、陽性と陰性であるが、これらの属性が個体ごとに異なって現れるのが、まさに個別相なのである。
人間の場合、個人ごとに性格(性相)が違い、体格や容貌(形状)が異なっている。また性相の陽陰や形状の陽陰も個人ごとに異なっている。例えば同じ喜び(情の陽)であっても、人によってその表現方法がそれぞれ異なっており、悲しみ(情の陰)においても同様である。鼻は体の陽的な部分であるが、鼻の高さと形は人によってそれぞれ異なっている。体の陰的な部分である耳の穴を見ても、その大きさとか形はやはり人によって異なっているのである。このように個別相は、普遍相それ自体が個別化されたものである。
種差と個別相
一定の事物が共通にもつ性質を徴 表(Merkmal)といい、同一の類概念に属する種概念のうちで、ある種概念に現れる特有の徴表を種差(specific difference)という。例えば「人」は「犬」や「猫」と同じように「動物」という類概念に属する種概念であるが、「人」という種概念に独特な徴表である「理性的」というのが人間の種差である。(統一思想から見るとき、徴表や種差も、共に普遍相の特殊化であることはもちろんである。)したがって、ある生物の徴表は、いろいろな段階の種差が合わさったものとなっているのである。
例えば一人の人間を考えてみよう。人間は生物でありながら、植物ではない動物の徴表すなわち種差をもっている。また動物として、無脊椎動物ではない脊椎動物の種差をもっている。また脊椎動物として、魚類や爬虫類ではない哺乳類の種差をもっている。また哺乳類として、食肉類や齧歯類ではない霊長類の種差をもっている。また霊長類として、テナガザルなどではないヒト科(Homonidae)の種差をもっている。またヒト科として、いわゆる猿人ではないヒト属(Homo)としての種差をもっている。またヒト属として、いわゆる原人ではないホモ・サピエンスの種差(理性的であるということ)をもっている。
このように人間の徴表にはおよそ、界(Kingdom)、門(phylum)、綱(class)、目(order)、科(family)、属(genus)、種(species)の七段階の種差が含まれている。そしてこのような七段階の種差の基盤のうえに、個人の特性すなわち個別相が立てられているのである。すなわち七段階の種差を土台とする個人の特性が人間の個別相である。
ところで人間における七段階の種差は、生物学者たちが便宜的にそのように分けただけであって、神はそのように、いろいろな種差を重ねながら人間を造られたのではない。『原理講論』に「神は人間を創造する前に、未来において創造される人間の性相と形状とを形象的に展開して、万物世界を創造された」(六七頁)とあるように、神は天宙の創造に際して、一番最後に造るべき人間を、心の中で一番初めに構想されたのである。
神は一番最初に構想した人間を標準として、動物、植物、鉱物の順で考えられたのである。すなわち構想した人間を標本として、動物を考え、次に植物を、その次に鉱物を考えられたのである。そのように、構想においては、人間、動物、植物、鉱物(天体)という順序で、下向式に考えられた。ところが実際に被造世界を造る順序はその逆であった。すなわち鉱物(天体)、植物、動物、人間の順序で、上向式に造られたのである。
神は人間の構想に際して、いくつかの種差を重ねながら構想されたのではない。一度にすべての属性(性相と形状、陽性と陰性)をもった人間を構想されたのである。しかも抽象的な人間ではなくて、具体的な個別相をもった人間、アダムとエバを心に描かれたのである。次に人間から一定の性質と要素を省略し、変形しながら、いろいろな動物を考えられた。次に動物の一定の性質と要素を省略し、変形しながら、いろいろな植物を構想された。また植物の一定の性質と要素を省略し、変形しながら、いろいろな天体と鉱物を構想された。そのような下向式の構想における一段階の構想、例えば動物の段階の構想においても、高級なものから始まって、そこから一定の性質と要素を省略または変形しながら、次第に低級な動物を構想されたのである(植物においても同様である)。したがって創造の結果だけを見れば、人間において、いろいろな段階の動物の種差が重なっているように見えるのである。
ここで留意すべきことは、分子、原子、素粒子など微視世界において、個体の個別相は、その個体が属する種類の種差(特性)と同一であるということである。例えば水の分子は、どんな分子であれ、同じ形態と化学的性質をもっている。原子においても同じであり、素粒子においても同じである。すなわち微視世界においては種差と個別相が一致すると見るのである。原子や素粒子はより高い次元の個体の構成要素になっているからである。鉱物の場合も同じである。鉱物からできている山河や宇宙の無数の天体にはそれぞれに個別相があるが、構成要素としての鉱物それ自体は、やはり種差がそのまま個別相となっているのである。
これは植物や動物においても同じである。すなわち種類の特性がそのまま個別相となるのである。例えば木槿の特性はそのまま、すべての木槿の個別相となり、一定の種類の鶏の特性は、そのまま同種のすべての鶏の個別相となる。そのように人間においては、個人ごとに個別相が異なるが、人間以外の万物は種類によって個別相が異なるのである。
個別相と環境
人間において、個別相とは個体が生まれつきもっている特性であるが、個別相にも環境によって変わる側面がある。それは原相がそうであったように、すべての個体は、存在または運動において、自己同一性と発展性(変化性)の両面を同時に現すからである。言い換えれば、人間は不変性(自己同一性)と可変性(発展性)の統一的存在として存在し、成長するのである。その中で不変的な側面が本質的であって、変化する側面は二次的なものである。個別相を遺伝学から見れば、遺伝形質に該当するということができる。この個別相が個体の成長過程において、環境との不断の授受作用を通じて部分的に変化していくのである。個別相のうち、このように変化する部分、または変化した部分を個別変相という。この個別相の可変的な部分は、遺伝学上の獲得形質に相当するといえる。
ソ連のルイセンコ(T.D. Lysenko, 1898-1976)は、春化処理(低温処理)によって、秋蒔き小麦を春蒔き小麦に変える実験を通じて、環境によって生物の特性が変化すると主張した。そして不変的な形質が遺伝子によって子孫に伝えられるとするメンデル・モルガンの遺伝子説を形而上学として否定した。生物の本来的な不変性を否定し、環境によって変化する面だけを強調したのである。このルイセンコの説は、スターリン(J.V. Stalin, 1879-1953)によって認められ、高く評価されて、それまでのメンデル・モルガン派の学者たちは反動として追放されるまでに至った。
しかし、やがてルイセンコ学説の誤りが外国の学者たちの研究によって確認され、メンデル・モルガンの学説の正当性が再び認められることになった。結局、ルイセンコ主義は唯物弁証法を合理化するための御用学説であることが暴露されたのである。こうした事実から見ても、万物は不変性と可変性の統一的存在であることを確認することができるのである。
個別相に関連して、環境が人間を規定するかという問題がある。共産主義は、人間の性格は環境によって規定されると主張しており、例えばレーニン(V.I. Lenin, 1870-1924)の革命家的人物としての指導能力は当時のロシアの状況から生まれた産物であるという。しかしながら統一思想から見るとき、人間はあくまでも環境に対して主体であり、主管主である。すなわち生まれつき突出した個性と能力をもった人間が、一定の環境条件が成熟したとき、その環境を収拾するために指導者(主体)として現れると見るのである。したがってロシア革命の場合、レーニンは本来、突出した能力の持ち主として生まれ、国の内外の条件が成熟した時に、持って生まれた能力を発揮して、環境を収拾しながらロシアを共産主義革命へと率いていったと見るべきである。
これを個別相という概念で表現すれば、環境は人間の個別相における可変的な部分に影響を与えるだけで、個別相全体が環境によって規定されるのではないのである。