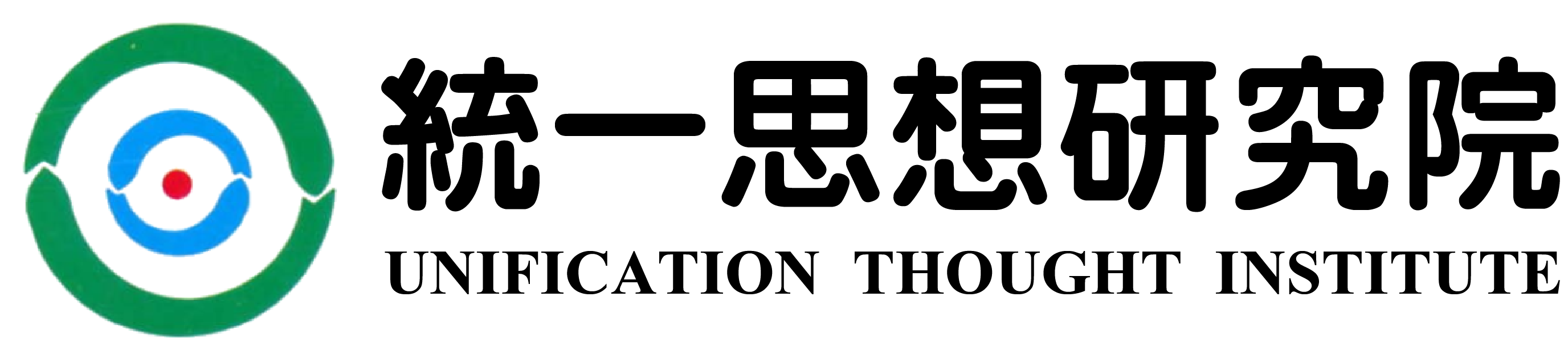(一)キルケゴール
キルケゴールの人間観
キルケゴール(S ren Kierkegaad, 1813-55)は、人間とは何かと自問し、「人間は精神である。精神とは何であるか。精神とは自己である。自己とは何であるか。自己とは自己自身にかかわる一つの関係である(7)」と答えている。それでは、このような関係を措定した者は誰か。それは自己以外の第三者でなければならない。それがすなわち神であるという。したがって、本来的自己とは神の前に立つ自己である。
ところが、本来、神と関係を結んで生きなければならない人間が、神から離れてしまった。そのいきさつは『不安の概念』の中に、聖書の創世記の物語を分析しながら、次のように書かれている。初めにアダムは平和と安息の状態にいたが、同時にそれは不安(Angst )な状態であった。神がアダムに「善悪を知る木から取って食べてはならない」と告げられたとき、アダムの中に自由の可能性が自覚された。そしてこの自由の可能性がアダムを不安に陥れた。そしてアダムが自由の深淵をのぞき見ることによって、めまい(Schwindel )を感じて、自己にとりすがった。そこに原罪が成立したのである。
その結果、人間は自己自身に対する関係のうちに分裂が起こり、絶望(Verzweifelung )に陥ってしまった。ところが人間は、その絶望を外から自分の身に降り懸かってくる何かのように思って、自分自身の力で絶望を取り除こうと努力する。けれども、それでは決して絶望を取り除くことはできない。信仰によって、神との関係を回復することによってのみ、本来の自己関係を取り戻すことができ、絶望から逃れることができるのである。
彼は「公衆は一切であって無である。あらゆる勢力のうちで最も危険なもの、そして最も無意味なものである(8)」といって、大衆の無責任さと良心のなさを批判した。そして人間が真の人間性を実現するためには、非人間的な大衆の世界から離れて、単独者として、ただ一人で神の前に立たなくてはならないと主張した。そして彼は、人間が本来的自己に帰っていく段階を実存の三段階として、次のように説明した。
第一の段階は、「美的実存の段階」である。この段階の人間は、ただ直接的に、あるがままに感性的な要求に従って、機智をもって生きようとするのであり、この段階の人間にとって人生の目的は享楽である。これはエロス的愛を追求する審美家、誘惑者の立場である。しかし、享楽の瞬間は継続して反復することは不可能であり、結局は倦怠と不安にとらわれる。そこで人間は挫折し、絶望する。しかし、決断によって次の段階に向かう。
第二の段階は、「倫理的実存の段階」である。この段階の人間は、良心を善悪の判断基準として生きようとする。すなわち責任感と義務感をもって善良な市民として生きようとする。しかし人間はいくら努力しても、全く良心に従って生きることはできない。そこで彼は再び挫折し絶望する。そして新しい決断によって次の段階に向かう。
第三の段階は、「宗教的実存の段階」である。信仰をもって、神の前にただ一人で立つ段階であり、そこで初めて人間は真の実存となる。この段階に入るには飛躍が必要である。それは知性では理解することができない逆説(パラドックス)を信じることによって可能である。例えば人倫に反する神の命令に服従して、息子のイサクを供え物として捧げたアブラハムの信仰や、永遠なる神が有限な時間の中で受肉し、人間(イエス)となって現れたというような、非合理的なことを信じるということである。そのような飛躍を通じて、初めて神との関係を回復することができるのである。アブラハムが人倫に反する神の命令に服従して、息子イサクを供え物として捧げようとした行為を、キルケゴールは宗教的な生の典型と見たのである。
そうして、神を中心とした実存、すなわち本来の自己になった人間が、「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」というイエスの言葉に従って、神を媒介とした愛によって互いに愛し合うとき、そのような「愛のわざ」によって、真の社会が成立すると彼は見たのである。
統一思想から見たキルケゴールの人間観
キルケゴールは、人間が神から離れることによって、「自己自身にかかわる関係」に分裂が起こり、不安と絶望に陥ったという。「自己自身にかかわる関係」とは、統一思想から見れば、心と体、あるいは生心と肉心の関係ということができよう。したがって「自己自身にかかわる関係」に分裂が起きたということは、人間が神から離れることによって、心と体が分裂してしまったことを意味するのである。言い換えれば、本来的自己においては、神を中心として心と体が一つになっていたのである。それでは、いかにしたら心と体は一つになることができるだろうか。それは神の心情を中心として、人間の生心と肉心が主体と対象の関係を回復して、円満な授受作用を行うことによって可能になるのである。
キルケゴールは、人間は単独者として神の前に立つとき、絶対者(神)に対して絶対的な関係に立つという。この単独者は統一思想における人間の本性の「個性体」に相当する概念である。しかし彼は、単独者はなぜ絶対的なものであるか説明していない。統一思想から見れば、人間の「個性体」が絶対的なのは、人間が絶対者である神の個別相に似ているからである。このようにキルケゴールの「関係性」と「単独性」は、統一思想の「心と体の統一的関係」と「個性体」の概念に相当するのである。
しかし統一思想から見るとき、このような理解は人間の本性のすべてに対する理解ではない。人間の本性の最も本質的な側面は心情的存在である。また人間は単独者として、すなわち個性体として神の前に立つというだけでは不完全な人間の理解である。男女が結婚して、夫婦として神の前に立つとき、初めて人間は完全なものとなるのである。人間は陽性と陰性の調和体であるからである。人間はまたロゴス的存在であり、創造的存在でもある。さらに主体性と対象性を共に備えた格位的存在でもある。単独者として、ひとり神の前に立つという彼の人間観は、真摯であるけれども、孤独で寂しいものとなっている。
人間はなぜ、神から離れるようになったのであろうか。その原因が明らかにならない限り、本来の自己、すなわち神の創造された状態の人間に帰ることは不可能である。キルケゴールは、アダムが自由の可能性からきた不安によって罪に落ちたといった。果たして、そうであろうか。統一原理によれば、自由や不安は堕落の原因ではない。人間始祖アダムとエバは、神のみ言を守らず天使長の誘惑に従って愛の方向性を間違ってしまったのである。すなわち、彼らは非原理的な愛の力によって堕落したのである。アダムとエバが神のみ言を守らないで脱線しようとするとき、彼らの本心の自由は、神の戒めを破ることに対する不安感を生ぜしめたのであり、その不安感は、かえって彼らが脱線しないように作用したのである。しかし非原理的な愛の力はこの不安感を抑え、彼らが堕落線を越えるようにさせたのである。こうした堕落の結果、人類は神から離れるようになり、そのため戒めを守らなかったことに対する罪悪感と、神からの愛の断絶によって、不安と絶望に陥るようになったのである。したがって堕落の問題を正しく解決しない限り、人間の不安と絶望の問題は根本的には解決できないのである。
キルケゴールの神の愛に関する概念も漠然としている。神の愛とは、温情をもって対象に対して無限に与えようとする情的な衝動である心情から生じるのであって、その神の愛が地上に現れるときに、方向性をもつ愛として現れる。すなわち、まず家庭を基盤として父母の愛、夫婦の愛、子女の愛、兄弟の愛などの分性的な愛として現れる。それがいろいろな方向に拡大されて、人類愛、民族愛、隣人愛、動物に対する愛、自然への愛などとして現れるのである。そのように神の愛には具体的な内容と方向性があるのであり、漠然とした愛ではないのである。
キルケゴールは、人間が本来の姿を回復するためには、大衆の虚偽と闘って神に帰らなくてはならないと訴えた。それは社会の迫害や嘲笑に耐えながら神にまみえようとした彼自身の歩みを反映したものであり、真実な信仰者になるように当時の宗教者たちに訴えた忠告でもあり、高く評価すべきである。
彼は二十七歳の時、十歳年下のレギーネ・オルセンと婚約したが、結婚によって彼女を不幸に陥れるのではないかという不安のために、また恋愛よりも次元の高い理想的な愛を実現しようとして、その一年後に一方的に婚約を破棄した。そのために、彼は社会的に非難されることとなったのであるが、統一思想から見るとき、彼は人格を完成した上で、神を中心とした真なる男女の愛を実現することを願ったと見ることができる。本来の人間像を捜し出そうとしたキルケゴールの方向性は、基本的には統一思想の立場と一致していたといえる。