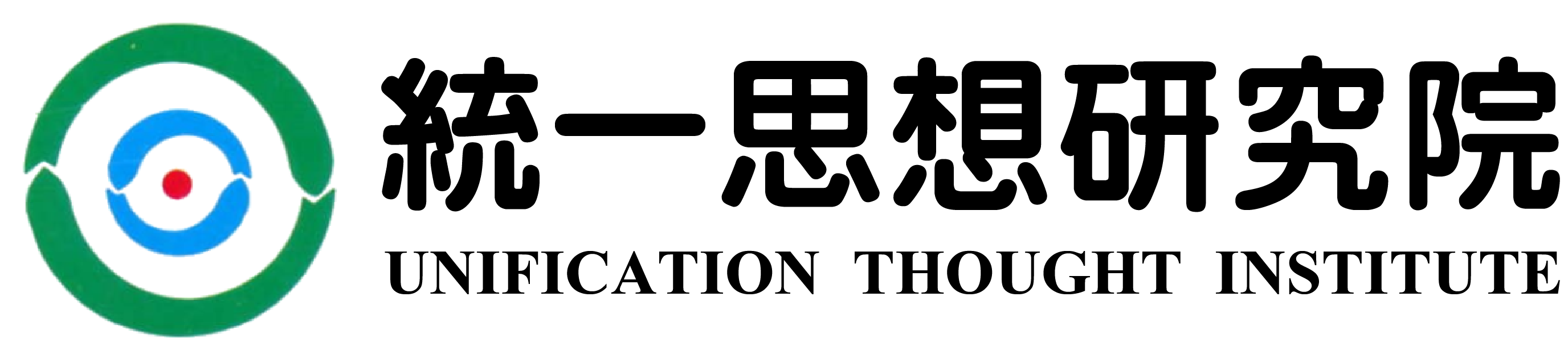(一) カント
カントの倫理観
カント(I. Kant, 1724-1804 )は『実践理性批判』において、真の道徳律は「何かの目的を実現するためには何々すべし」という仮言命法(Hypothetischer Imperativ )であってはならず、無条件に「何々すべし」という定言命法(Kategorisher Imperativ )でなければならないと主張した。例えば「立派な人だといわれるために正直にせよ」というのではなく、「正直であれ」という無条件的な命令でなくてはならないという。定言命法は実践理性によって立てられるものであるが、それがわれわれの意志に命令を与えるのである(このような実践理性を「立法者」という)。この実践理性の命令を受けた意志が善意志である。そして善意志が行動を促すのである。
カントは、道徳の根本法則を次のようにいい表した。「汝の意志の格率が、いつでも同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為せよ(3)」。ここで格率(Maxime)とは、個々人が主観的に決める実践の原則をいうのであり、そのような主観的な原理(格率)が普遍性を帯びるような立場において行為せよということであった。カントは、あたかも自然法則のように、矛盾なく普遍的に妥当するものを善とし、そうでないものを悪としたのである。
カントは、人間の内なる道徳律は義務の声としてわれわれに迫ってくるといった。「義務よ! 君の崇高にして偉大なる名よ。この名を帯びる君は、媚び諂って諸人に好かれるものを何ひとつ持合わせていないのに、ひたすら服従を要求する。……おのずと人の心に入り来たり、いやでも敬意を獲ち得るような法則を打ち立てるだけである(4)」。カントの主張した道徳は、義務の道徳であった。
カントはまた、善意志が何ものによっても規定されないためには、自由が要請されなければならず、不完全な人間が完全に善を実現しようとする限り、霊魂の不滅が要請されなければならず、また完全なる善すなわち最高善を追求するとき、それが幸福と一致することが可能になるためには、神の存在が要請されなければならないといった。このようにしてカントは霊魂の存在と神の存在を実践理性の要請(Postulat)として認めたのである。
統一思想から見たカントの倫理観
カントは純粋理性(理論理性)と実践理性を区別した。純粋理性とは認識のための理性であり、実践理性とは意志を規定し行為へと導く理性である。ここに純粋理性と実践理性を分離したことによって、定言命法による行為がなぜ善なのかという問題が生じざるをえない。ある行為が善かどうかを決定しなければならない場合、その行為の結果を確認しなければならないからである。ところがカントは、結果がいかなるものにせよ、「何々すべし」という定言命法に従った行為であれば善だというのである。
Aという人が道で苦しんでいるBという人に出会ったとする。そこで「Bを助けよ」という内面からの定言命法に従って、AはBを病院に連れていこうとしたとする。ところがBは人の世話になることを願わない人であるかもしれない。するとBは助けを断って、一人で病院に行こうとするであろう。しかしAは実践理性の下した定言命法に従ったのだから、それによって満足するであろう。そのときAの行為はAには無条件に善になるであろうが、Bには有り難迷惑であって善とは感じられないのである。
そのように、結果を確認しないで動機だけ良ければそれで足りるとするのがカントの立場であって、それは常識的な善の概念に合わないのである。これはカントが純粋理性と実践理性を、すなわち認識と実践を分離したために生じたアポリア(難点)である。実際は純粋理性と実践理性は二つに分かれたものではない。理性は一つであって、その一つの理性に従って結果を確認しながら行為するのが、実際のあり方なのである。
またカントの道徳律において、主観的な格率を普遍化させる場合、その基準は何か、そしていかにしてそのような普遍化が可能になるかということも問題となる。またカントは一方で、すべての人々が完全に道徳的になれば、それによって幸福が実現されるであろうといいながら、他方では、幸福を目的とする行為は仮言的だから善とはいえないという。人間が幸福を求めていることを知りながら、幸福を目的として行動してはならないというのである。そして彼は神を要請して、完全に善を行えばその状態が幸福であろうという。
このようなカントのいろいろな問題点は、すべてカントが神の創造目的が分からなかったことに起因している。彼は、目的といえば、無条件に自愛的、利己的なものであると考えたのである。統一思想から見れば、創造目的には全体目的と個体目的があるのであって、人間は本来、全体目的を先に立てながら個体目的を追求するようになっている。ところが彼は、目的というとき、もっぱら個体目的だけを考えたのである。その結果、彼はすべての目的を否定してしまい、その道徳律は基準が曖昧なものとなってしまったのである。
さらにカントは、一方では、道徳律が成立するためには霊魂の不滅と神の存在が要請されなければならないと主張したが、他方では、『純粋理性批判』において明らかにしているように、神や霊魂には感性的内容がないから、その認識は不可能であるといって、それらを排除したのである。そこにカント哲学のアポリアがあった。カントは神を要請するといったが、それは仮定的な神であって、真の神や実在する神ではないために、決してわれわれが信じ、頼ることのできる神ではなかったのである。
そしてカントは、実践理性に基づく義務感だけを善の基準と見なした。しかしながら、義務それ自体は冷たいものであるので、カントのいう善の世界は冷たい義務の世界、冷え冷えとした規律だけを守らなくてはならない兵営のような世界であった。統一思想から見れば、義務や規律はそれ自体で目的とはなりえない。目的は真なる愛を実現することにあるのであり、義務や規律は真なる愛を実践するための方便にすぎないからである。