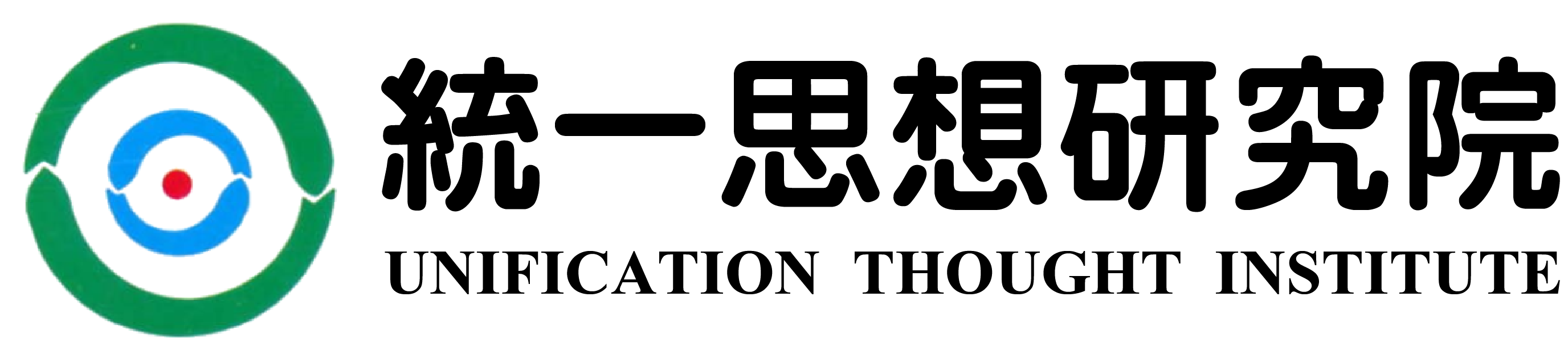五 従来の歴史観
次は代表的な従来の歴史観の要点を紹介する。従来の歴史観と統一史観の比較において、参考になるからである。
循環史観(運命史観)
ギリシア人は、毎年、春夏秋冬が反復し、循環しているように、歴史も循環的に変化していると考えた。歴史的事件の発生と消滅は運命的なものであって、人間の力ではどうすることもできないだけでなく、歴史には意味もなく目標もないと見る立場が循環史観または運命史観の立場である。代表的な歴史家は「歴史の父」と呼ばれ、『歴史』(Historiai)を書いたヘロドトス(Herodotos, ca.484-425 B.C.)と、『ペロポネソス戦史』を書いたツキディデス(Thukydides, ca. 460-400 B.C.)である。運命論者であるヘロドトスは、ペルシア戦争のくだりを物語的に描き、ツキディデスはペロポネソス戦争を始めから終わりまで忠実に写実的に描いた。両者共に共通するのは、歴史は繰り返しているという考え方であった(12)。
循環史観は歴史の経路を必然的(運命的)なものとして理解したのであり、人間の努力によって歴史の動向が左右される事実を認めず、また歴史には目標はないのだから未来像を提示することもできなかった。
摂理史観
歴史には始まりも終わりもなく、目標もなく、循環運動を反復するだけであると見るギリシアの歴史観に対して、キリスト教は歴史には始まりがあり、一定の目標に向かって直線的に進行するなど、循環史観とは根本的に違う歴史観を提示した。すなわち歴史は人間の創造と堕落から始まり、最後の審判に至る救済の歴史であり、歴史を動かしているのは神の摂理であるという主張である。これを摂理史観またはキリスト教史観という。
キリスト教史観を体系化したのがアウグスティヌス(Augustinus, 354-430 )である。アウグスティヌスは、彼の書いた『神国論』において、歴史は神を愛する人々の住む神の国(Civitas Dei )と悪魔に誘惑された人々の住む地の国(Civitas terrena )との闘争の歴史であると見たのであり、最後に神の国が勝利して永遠の平安を得るとした。このような歴史の進行は、神があらかじめ定めた計画に従うものであった。
彼は堕落から救済に至るまでの人類の歴史を次の六つに区分した。(1)アダムからノアの洪水まで、(2)ノアからアブラハムまで、(3)アブラハムからダビデまで、(4)ダビデからバビロン捕囚まで、(5)バビロン捕囚からキリストの誕生まで、そして(6)キリストの初臨から再臨までである。最後の六番目の期間がどのくらい続くかは明らかにしなかった。
このようなキリスト教史観によって、歴史は目標に向かう意味ある歴史として映るようになったが、人間は神によって動かされる道具的存在にすぎなかった。そしてその歴史観の内容は神秘的なものを含んでおり、論理性や法則性が欠如していて、今日に至っては社会科学として受け入れがたいものとなっている。
精神史観(進歩史観)
ルネサンス時代に入ると、神学的な歴史観が次第に影をひそめ、十八世紀の啓蒙主義に至ると、歴史を動かしているのは神の摂理ではなくて人間であると考える、新しい歴史観が出現した。歴史は人間の精神の進歩に従って、ほぼ一直線に、そして必然的に進歩していくと見る立場であった。これを精神史観あるいは進歩史観という。
ヴィコ(G. Vico, 1668-1744 )は、歴史における神の摂理を認めていたが、世俗の世界は人間がつくったものであるから、歴史は神の意志だけでは説明することはできないといった。歴史の把握において、神は背後に隠れ、人間が前面に出されたのである(13)。
ヴォルテール(Voltaire, 1694-1778 )は、歴史に作用する神の力を排除した。歴史を動かしているのは神ではなくて、高い教育を受けた科学を取り入れた人々、すなわち啓蒙家であるといった。
コンドルセ(Condorcet, 1743-94 )は、人間の理性を覚醒すれば、歴史は科学的にも倫理的にも調和しながら進歩すると主張した。
カント(I. Kant, 1724-1804 )は、歴史の目的は人間のあらゆる高貴な才能の、諸民族の結合体における実現であるとして、「世界市民的意図における人類の歴史」を提言した。
ロマン主義の哲学者ヘルダー(J.G. Herder, 1744-1803 )は、人間性の発展が歴史の目標であるといった。
ヘーゲル(Hegel, 1770-1831 )は、歴史を「精神の自己実現」あるいは「理念の自己実現」と見た。理性が世界を支配し、世界史は理性的に進行するという見解であり、世界を支配している理性を彼は世界精神と呼んだ。世界を支配している理性は、人間を操りながら活動しているといい、それを理性の詭計と称した。ヘーゲルの歴史観は特に精神史観または観念史観といわれている。ヘーゲルはプロシアにおいて自由の理念が実現した理性国家が到来すると見たが、実際はそうではなく、かえって搾取や人間疎外などの反理性的な社会問題が深まってきた。そのようなヘーゲルの歴史哲学に反旗を翻して現れたのが唯物史観であった。
唯物史観
ヘーゲルは理性または理念が歴史を動かしているという精神史観を主張したが、それに対してマルクスは歴史を動かしている原動力は物質的な力であると主張し、唯物史観(革命史観ともいう)を提示した。
唯物史観によれば、歴史を動かしているのは理念とか精神の発展ではなくて、生産力の発展である。生産力の発展に相応して一定の生産関係が成立するが、生産関係はいったん成立すると、間もなく固定化して、ついには生産力の発展に対して桎梏化する。そこに古い生産関係を維持しようとする階級(支配階級)と、新しい生産関係を求める階級(被支配階級)との間に階級闘争が展開される。したがって歴史は階級闘争の歴史とならざるをえない。資本主義社会において階級闘争が極に達すると、被支配階級であるプロレタリアートが支配階級であるブルジョアジーを打倒する。そして階級のない「自由の王国」である共産主義社会が実現するというのである。
この唯物史観が誤りであったことは今日の共産主義の終 焉がよく物語っている。理論的な面から見ると、唯物史観の法則はみな独断的な主張にすぎなかった。例えば唯物史観は生産力の発展を物質的な発展と見ているが、生産力がいかにして発展するのかということに対して唯物弁証法的な説明がなされなかった。また人類歴史は階級闘争による社会変革の歴史であるというが、そう主張するだけで実際に階級闘争によって社会が変革された例は一度もなかった。このように唯物史観はすべてが虚構の理論であったのである。
生の哲学の史観
ディルタイ(W. Dilthey, 1833-1911 )およびジンメル(T. Simmel, 1858-1918 )は「生の成長」とともに歴史は成長すると主張した。これを生の哲学の史観という。
ディルタイによれば、生は人間的体験であるが、体験は必ず表現されて外の世界に表れるようになる。そうして現れたものが歴史的世界であり、文化の世界である。したがって宗教、哲学、芸術、科学、政治、法律などの人間の文化体系は生の客観化したものである。
ジンメルも同様に、歴史とは生の表現であると主張した。生とは無限に続く流動である。そして生(精神的な生)の生成の流れが歴史となるのである(14)。
ところで生の哲学の史観によれば、歴史上に現れる人間の苦痛や不幸を生の成長に付随して現れる不可避的な現象と見なす。したがって人間がいかにして苦痛や不幸から解放されるかという問題は、この哲学によっては解決することはできなかった。
文化史観
第一次世界大戦前まで、ヨーロッパにおいて、歴史の進歩や発展に対する信頼は基本的には揺らいでいなかった。そして歴史はヨーロッパを中心として発展していると人々は信じていた。そのような直線的で、ヨーロッパ中心の歴史像を粉砕したのがシュペングラー(O. Spengler, 1880- 1936 )であった。
シュペングラーは歴史の基礎は文化であるとして文化史観を唱えた。彼は、文化は有機体であると見た。有機体である以上、文化は生まれるとともに成長し、やがて滅びるのであり、文化の死滅は不可避的な運命であるとした。そして彼は西洋文明の中に、ギリシア=ローマの没落に対応する徴候を見いだして、西洋の没落を預言した。そのように西洋の没落を予知しながらも、ペシミズムに陥ることなく、不可避的な運命をたじろがないで引き受けて生きることを説いた。そこにはニーチェとの強いつながりがあった。シュペングラーの歴史観は決定論的であった。
シュペングラーの影響を受けながら、独自の文明史観を打ち立てたのがトインビー(A.J. Toynbee, 1889-1975)である。トインビーによれば、世界史を構成する究極的な単位は地域でも、民族でも、国家でもなく、個々の文明であった。そして文明は誕生( genesis )、成長(growth )、挫折(breakdown )、解体( disintegration )、消滅(dissolution )の段階を経るとした。
文明発生の原因は、自然環境や社会環境からの挑戦(challenge)に対する人間の応戦( response )にある。創造的少数者が大衆を導きながら文明を成長させてゆくが、やがて創造的少数者が創造性を失うと文明は挫折する。そのとき創造的少数者は支配的少数者に転化し、文明の内部には「内的プロレタリアート」が、周辺には「外的プロレタリアート」が生まれ、支配的少数者から離反する。そうして世が乱れ、混乱期を迎えるようになるが、やがて支配的少数者のうちの最強のものによって、「世界国家」が打ち立てられて混乱期は終わる。世界国家による圧政のもとで、内的プロレタリアートは「高等宗教」をはぐくみ、外的プロレタリアート(周辺の蛮族)は「戦闘集団」(侵略勢力)を形成する。そして世界国家、高等宗教、戦闘集団の三者が鼎立する。やがて高等宗教は支配層を改宗させることにより「世界宗教」となるが、世界国家は間もなく崩壊し、それとともに文明は死を迎えるのである。
こうして一つの文明が消滅したのちに、外的プロレタリアートが侵入するが、外的プロレタリアートが高等宗教に改宗することによって次代の文明を誕生させる。この文明の受け継ぎを「親子関係」という。世界史の中で発生し、十分に成長した文明は二十一であったが、現存する文明はすべて三代目に属するのであって、キリスト教文明(西洋とギリシア正教圏)、イスラム教文明、ヒンドゥー教文明、極東文明の四つの系譜に分かれているという。トインビーの主張した三代にわたる文明の継承は、統一史観における、復帰基台摂理時代、復帰摂理時代、復帰摂理延長時代という三代の摂理的同時性と対応するものと見ることができる。
トインビーの歴史観の特徴は決定論を排除し、非決定論、自由意志論を主張したことにある。つまり挑戦に対していかに応戦するかということは、人間の自由意志にかかっているのである。したがって歴史の進む道は決して、あらかじめ決定されているのではなく、人間は未来を選ぶことができるのである。
トインビーは人類歴史の未来像として明らかに神の国(Civitas Dei)を描いている。しかし非決定論の立場から、「神の国」か「闇の国か」という未来の選択は、人類の自由意志にかかっているとした。彼は次のようにいっている。
神自身の「存在」の法である愛の法のもとで、神の自己犠牲は、人類の前に霊的な完成という理想を据えることで、人類に挑戦している。そして人類には、この挑戦を受けいれるか拒否するかの完全な自由がある。愛の法は、人類が罪人になるか聖者になるかを人類の自由に任せている。つまり、愛の法は、人類の個人的および社会的生活を「神の国」への前進たらしめるか、闇の国への前進たらしめるかの選択を人類の自由に任せているのである(15)。
トインビーの歴史観のもう一つの特徴は、近代社会が忘却したかに見えた神を歴史観の中に再び導入したということである。彼は次のように語っている。
自分は、歴史とは、真剣に神を求める人々に、御業によって自らを示し給う神の御姿の、朧ろげでまた不完全な影像に外ならないと思う(16)。
歴史観の変遷と統一史観
以上、従来の歴史観の概略について述べたが、ここで従来の歴史観と統一史観を比較し、統一史観が従来の歴史観を統一しうるものであることを見てみよう。
第一に、歴史を円環運動と見るか直線運動と見るかという問題がある。ギリシアの循環史観、シュペングラーの文化史観は歴史を円環運動としてとらえたが、キリスト教史観や進歩史観、唯物史観は歴史を直線運動としてとらえた。一方、生の哲学史観は流動する生の成長とともに歴史は発展するとしたが、これは進歩史観の変形と見ることができよう。
歴史を直線運動としてとらえると歴史の発展に希望を抱くことができるが、人類歴史における挫折と復興の意義が理解できない。他方、歴史を円環運動としてとらえるとき、国家や文化の滅亡は運命的なものとなって希望を見いだすことはできない。
統一史観は、再創造と復帰という二つの面から、歴史を直線的な前進運動と円環運動の二側面をもった螺旋形運動としてとらえる。すなわち歴史は目標——創造理想世界の実現——に向かって発展していくという前進的性格とともに、摂理的人物を立てて、蕩減の法則によって、失われた創造理想世界を復帰するという円環運動の性格を合わせてもった螺旋形運動の歴史であったと見るのである。
第二に、決定論か非決定論かという問題がある。歴史は運命に従って必然的に運行するというギリシアの運命史観やシュペングラーの文化史観は決定論であった。歴史は神の摂理に従って進行しているとする摂理史観も決定論であった。理性または世界精神が歴史を動かしているとするヘーゲルの精神史観や、歴史は生産力の発展に従って必然的に共産主義社会に到達するという唯物史観も決定論であった。これらはみな人間を超えた、ある力が歴史を動かしているという見解であった。このような決定論から見るとき、人間は常に歴史の力や法則に引きずられている受動的な存在にすぎず、人間の自由意志による努力によって、歴史を変えていくことは不可能となっていた。
一方、トインビーは自由意志論の立場から非決定論を主張した。つまり、人間の自由意志によって歴史の進む道は選択されると主張した。しかしトインビーの非決定論の立場においては、歴史の未来像は不明であって、未来に希望をもつことができなかった。
それに対して統一史観は、歴史の目標は決定的であるが、摂理的な事件の成就には神の責任分担のほかに人間の責任分担の遂行を必要とするという観点から、歴史の過程は非決定的であると見る。すなわち統一史観は決定論と非決定論の両側面をもつのであり、このような理論を責任分担論という。
このように従来の歴史観と統一史観を比較してみると、従来の歴史観はそれぞれ統一史観の一側面を強調していたことが分かると同時に、統一史観が総合的、統一的な歴史観であることが分かる。ところでトインビーの歴史観には統一史観に似た内容が多くある。摂理的に見るとき、トインビーの歴史観は統一史観が出現するための前段階を準備した史観であるといえる。言い換えれば、トインビーの歴史観は従来の歴史観と統一史観を連結する橋の使命をもっていたと見ることができる。