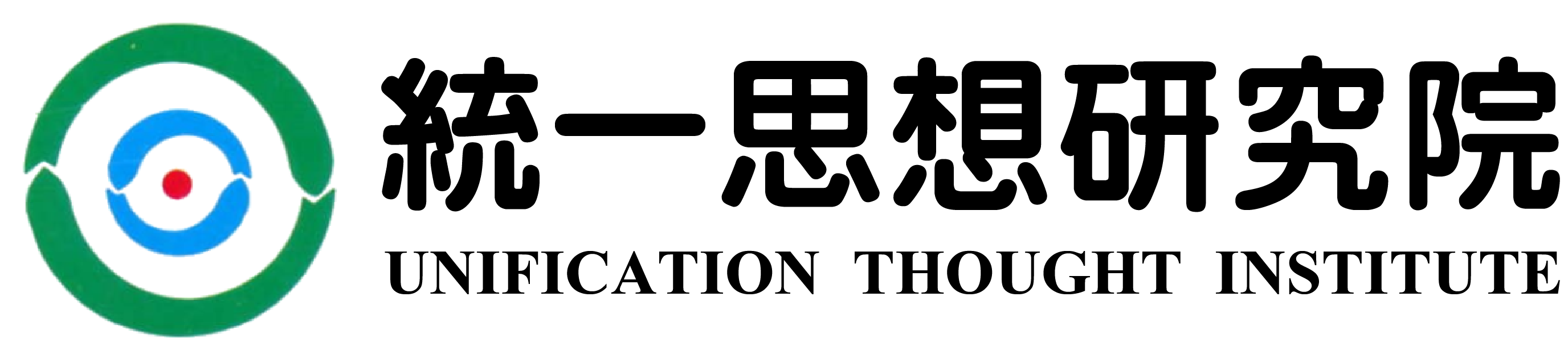(一) 認識の起源
すべての知識は経験から得られると見るのが経験論であり、それに対して真なる認識は経験から独立した理性の作用によって得られると見るのが理性論または合理論である。いずれも十七—十八世紀に現れたのであるが、イギリスの哲学者たちは経験論を説き、大陸の哲学者たちは理性論を説いた。
(1) 経験論
ベーコン
経験論の基礎を確立したのはフランシス・ベーコン(F. Bacon, 1561-1626 )である。彼は著名な著作『ノーウム・オルガヌム』(新オルガノン、Novum Organum, 1620 )において、彼は伝統的な学問は無用な言葉の連続にすぎず、内容的には空虚であるといい、正しい認識は自然の観察と実験によって得られると主張した。そのとき、正しい認識を得るためには、まず先入的な偏見を捨て去らねばならないとして、その偏見として四つの偶像(Idola 、イドラ)を挙げた。
第一は、種族の偶像(Idola Tribus )である。これは、人の知性は平らでない鏡のようなものであるために、事物の本性をゆがめて写しやすいという、人間が一般に陥りやすい偏見をいう。例えば、自然を疑人化させて見る傾向がそうである。
第二は、洞窟の偶像(Idola Specus )である。これは、あたかも洞窟の中から世界を眺めるように、個人の独特な性質や習慣や狭い先入観などによって生じる偏見である。
第三は、市場の偶像(Idola Fori )である。これは、知性が言葉によって影響されるところからくる偏見をいう。そのため全く存在しないものに対して言葉が作られ、空虚な論争がなされることもある。
第四は、劇場の偶像(Idola Theatri )である。これは、権威や伝統に頼ろうとするところから来る偏見をいう。例えば、権威のある思想や哲学に無条件に頼ろうとするところからくる偏見などがそれである。
このような四つの偶像を取り除いてから、われわれは自然を直接観察して、個々の現象の中にある本質を見いださなければならないといって、ベーコンは帰納法を提示した。
ロック
経験論を体系づけたのはロック(J. Locke, 1632-1704 )であり、主著『人間悟性論』において、その主張を詳細に展開した。彼はまず、認識における生得観念を退けた。生得観念とは、人間が生まれつきもっている、認識に必要な観念のことをいうのである。彼は、人間の心は本来、白紙(タブラ・ラサ、tabula rasa )のようなものであり、白紙に文字や絵を書けばそのまま残るように、心に入った観念は心の白紙にそのまま書かれる(認識される)といった。つまり彼は、認識は外部から心に入ってくる観念によってなされると見たのである(2)。
ところで、観念は二つの方向から心に入ってくるのであるが、一つは感覚(sensation)の方向であり、もう一つは反省(reflection)の方向である。それが認識の起源である。すなわちロックにおいては、感覚や反省を通じた経験が認識の起源である。感覚とは、感覚器官に映る対象の知覚のことをいう。すなわち黄色い、白い、熱い、冷たい、柔らかい、堅い、苦い、甘いなどの観念をいうのである。反省とは、心の作用をいい、考える、疑う、信ずる、推理する、意志するなどがそれである。この反省の時にも観念が得られる。
ところで、観念には単純観念(simple idea )と複合観念(complex idea )があるという。単純観念とは、感覚と反省によって得られる、個々ばらばらに入ってくる観念であり、それらが悟性の働きによって、結合、比較、抽象されることによって、より高次の観念をなしたものが複合観念である。
そして単純観念には、固体性(solidity )、延長(extension )、形象(figure )、運動(motion )、静止(rest )、数(number )のように、対象自体に客観的に備わっている性質と、色(color )、香(smell )、味(taste )、音(sound )のように、主観的にわれわれに与えられる性質があるとして、前者を第一性質、後者を第二性質と呼んだ。
複合観念には、様相(mode )、実体(substance )、関係(relation )の三つがある。様相とは、空間の様相(距離、平面、図形など)、時間の様相(継起、持続、永遠など)、思惟の様相(知覚、想起、推理)、数の様相、力の様相など、事物の状態や性質、つまり属性を表す観念である。実体とは、単純観念を起こす物自体をいうのであり、諸性質を担っている基体(substratum )いわゆる物自体に対する観念である。そして関係とは、因果の観念のように、二つの観念を比較することによって生ずる観念(同一、差異、原因、結果など)をいう。
ロックは、「[認識とは]われわれのもつ観念の間にある結合と一致、または不一致と背反の知覚である(3)」と見た。そして、「およそ真理とは、観念の一致不一致をそのとおりに言葉で記すことである(4)」と述べた。そして彼は、観念の分析を行うことによって、認識の起源の問題に答えようとしたのである。
ロックは、直覚的に認識される精神と、論理的に認識される神の存在を確実なものと考えた。ところで、外界における物体の存在は否定できないとしても、感覚的にしか知りえないから確実性をもつことはできないとした。
バークリ
バークリ(G. Berkeley, 1685-1753 )は、ロックのいう物体の第一性質と第二性質の区別を否定し、第一性質も第二性質と同様に主観的であるといった。例えば距離は、客観的に存在するもの(延長)、つまり第一性質の観念のように見えるが、それも主観的なものだというのである。距離の観念は、次のようにして得られる。すなわち、われわれは一定の距離の向こう側にある事物を目で見て、次にそこまで足で地を踏んで歩いて行き、手で触れる。そのような過程を繰り返すとき、ある種の視覚はやがてある種の触覚(例えば歩く時の足の裏の触覚)を伴うであろうことを、あらかじめ予想するようになる。そこに距離の観念が生じるのである。つまり、われわれは延長としての距離をそのまま客観的に見ているのではないのである。
バークリは、ロックのいう諸性質の担い手としての実体をも否定し、事物は観念の集合(collection of ideas)にすぎないとした。そして、「存在とは知覚されるということである」(esse is percipi)と主張した。このようにしてバークリは、物体という実体の存在を否定したが、知覚する実体としての精神の存在については少しも疑わなかった。
ヒューム
経験論を究極まで追究したのがヒューム(D. Hume, 1711-76 )であった。彼は、われわれの知識は印象(impression)と観念(idea)に基づいていると考えた。印象とは、感覚と反省による直接的な表象をいい、観念とは、印象が消えたのちに記憶または想像によって心に表れる表象をいう。そして、印象と観念の両者を総称して知覚(perception)と呼んだ。
彼は、単純観念の複合に際して、類似(resemblance)、接近(contiguity)、因果性(cause & effect)を三つの連想法則として挙げた。ここで、類似と接近に関する認識は確実なものであって問題はないが、因果性に関しては問題があるという。
彼は、因果性に関する例として、稲妻が光ったのちに雷の音を聞いたとすれば、普通、人は稲妻が原因であり、雷鳴が結果であると考えるが、ヒュームは単なる印象としての両者を原因と結果として結びつける理由は何もないといい、因果性の観念は主観的な習慣や信念に基づいて成立するものであるという。また鶏が鳴いたのちに、しばらくして太陽が上るということは経験的に誰でも知っている現象であるが、そのとき、鶏が鳴くことが原因で、太陽が上るのがその結果だとはいえない。因果性として考えられている認識は、そのように主観的な習慣や信念に基づくものであるという。
このようにして経験論はヒュームに至り、懐疑論に陥ってしまった。彼はまた、実体性の観念については、バークリと同様に、物体という実体の存在を疑った。さらに彼は、精神(心)という実体の存在までも疑ったのであり、それは知覚の束(bundle of perceptions )にほかならないと考えた。
(2) 理性論
以上のような英国の経験論に対して、感覚によっては正しい認識は不可能であり、理性による演繹的、論理的な推理によってこそ正しい認識が得られると見る立場が、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、ヴォルフなどを中心とした大陸の理性論(合理論)である。
デカルト
理性論の始祖とされるデカルト(R. Descartes, 1596-1650 )は、真の認識に至るために、すべてのものを疑うことから出発する。それがいわゆる方法的懐疑(methodical doubt )と呼ばれるものである。
彼はまず、感覚はわれわれを欺くと考えて、すべての感覚的なものを疑った。なぜ彼はそのような方法を取ったのだろうか。それは真なる真理を得るためであった。すなわちこの世界のすべてを疑い、甚だしくは自分自身までも疑ってみて、それでもなお疑いえないものがあるとすれば、それはまさに真実であり、真理であるからである。それで彼は、可能な限りあらゆるものを疑い、また疑ったのである。その結果、一つの事実のみは疑いえないことを彼は悟ったのである。それはわれが疑う(思推する)という事実である。そこで彼は、「われ思う、ゆえにわれあり」( Cogito, ergo sum )という有名な命題を立てたのである。
この「われ思う、ゆえにわれあり」という命題がデカルトのいう哲学の第一原理であるが(5)、この命題が間違いなく確実であるのは、この認識が明晰(clear )かつ判明(distinct )であるからだという。したがってここに、「われわれがきわめて明晰に判明に理解するところのものはすべて真である(6)」という一般的規則(第二原理)が引き出されるのである。ここで明晰(clear )とは、事物が精神に明確に現れることをいい、判明(distinct )とは、明晰であるとともに、他のものから確実に区別され、粉らわしくないことをいう(7)。明晰の反対が曖昧(obscure )であり、判明の反対が混同(confused )である。
ここに、思惟を属性とする精神と、延長を属性とする物体の存在が確実なものとして認められる。すなわち、第一原理と第二原理からデカルトの物心二元論が成立する。第一原理から「心」(思惟)の実在が、第二原理から「物質」(延長)の実在が証明されるのである。
ところで、明晰かつ判明なる認識が確実であることが保証されるためには、悪霊がひそかに人を欺いているというようなことがあってはならない。そのためには神の存在が必要とされる。誠実なる神が人間を欺くことはありえないから、神が存在するとすれば、認識に誤りが生ずるはずがないのである。そして彼は、次のようにして神の存在を証明した。
第一に、神の観念はわれわれのうちにある生 得観念(本有観念)であるが、その観念が存在するためには、必ずその原因がなくてはならないのである。
第二に、不完全なわれわれが完全な存在者(神)の観念をもつということから神の存在が論証される。
第三に、最も完全な存在者(神)の概念は、その本質としての実体が必然的に存在するということを含んでいることから、神の存在が論証される。
このようにして神の存在が証明された。したがって神の本質である無限、全知、全能が明らかになり、さらに神の属性の一つとして誠実性(veracitas )が保証される。そして明晰・判明なる認識に確実な保証が与えられるようになるのである。デカルトは、神と精神と物体(物質)の存在を確実なものとしたが、その中で真の意味での独立的な存在は神のみであり、精神と物体は神に依存している存在であると考えた。そして精神と物体は、それぞれ思惟と延長をその属性とする、相互に全く独立した実体であるとして、彼は二元論を主張した。
以上のように、デカルトは明晰・判明なる認識は間違いなく確実であるということを論証したが、彼はそれによって数学的方法に基づいた合理的な認識の確実さを主張しようとしたのである。
スピノザ
スピノザ(B. de Spinoza, 1632-77 )も、デカルトと同様に、厳密な論証によって真理を認識することができると考え、特に幾何学的方法を哲学に用いて論理的な理論展開をしようとした。
理性によって、一切の真理を認識することができるというのがスピノザの哲学の前提である。すなわち、理性によって「永遠の相のもとに」事物をとらえ、さらに神との必然の関係において全体的、直覚的にとらえるとき、真なる認識が得られるのである。ここで「永遠の相のもとに」事物をとらえるということは、すべてのものを必然の過程において(必然の連続から)理解するという意味である。そうした立場からすべての事物を見るとき、人ははかない事物、流れいく現象に執着し、心を煩わされなくてもよいのであり、むしろ今まで、はかないものと思っていた事物や現象、さらにはわれわれ自身までも、神の永遠の真理の表現として、貴重なものとしてとらえられるようになるのである。そのとき、真なる生命を得て、完全に到達し、無限な喜び、真なる幸福を得るようになるのである。これが永遠の相のもとに事物をとらえるということの意味である。
またそれは、明晰・判明な理性と霊感によって得られる自覚であるという。彼は認識を「感性知」、「理性知」、「直覚知」の三つに分けた。そのうち、知性による秩序づけのない「感性知」は不完全なものであり、「理性知」と「直覚知」によって真なる認識が成立すると考えた。ここにスピノザのいう直覚知とは、あくまで理性に基づいたものであった。
デカルトが精神と物質を、それぞれ思惟と延長をその属性とする互いに独立した実体であると考えたのに対して、スピノザは実体は神のみであり、思惟と延長は神の属性であるとした。彼は神と自然の関係を、能産的自然(natura naturans )と所産的自然(natura naturata )の関係であると見て、両者は切り離すことができないといい、「神は自然である」という汎神論的思想を展開した。
ライプニッツ
ライプニッツ(G.W. Leibniz, 1646-1716 )も数学的方法を重んじ、少数の根本原理からあらゆる命題を導いてゆくことを理想と考えた。彼は、人間の認識する真理を二つに分けた。すなわち、第一に純粋に理性によって論理的に見いだされるもの、第二に経験によって得られるものに分けて、前者を「永遠の真理」または「理性の真理」と名づけ、後者を「事実の真理」または「偶然の真理」と名づけた。理性の真理を保証しているのは同一律と矛盾律であるが、事実の真理を保証するのは「いかなるものも十分な理由なくして存在しえない」という充足理由律であるとした。
しかしこのような真理の区別は、人間の知性に対してのみあてはまるものであり、人間において事実の真理と見なされるものも、神は論理的必然性によって認識しうると見ているのである。ゆえにライプニッツにおいて、究極的に理性的認識が理想的なものと思われたのである。
彼はまた、真なる実体は宇宙を反映する「宇宙の生ける鏡」としてのモナド(monade 、単子)であるとした。モナドは、知覚と欲求の作用をもつ非空間的な実体であり、無意識的な微小知覚(petite perception )から、その集合としての統覚(apperception )が生じるといった。そしてモナドには、物質の次元の「眠れるモナド」、感覚と記憶をもつ動物の次元の「魂のモナド」(または「夢みるモナド」)、普遍的認識をもつ人間の次元の「精神のモナド」の三段階のモナドがあり、最高次元のモナドが神であるといった。
ヴォルフ
ライプニッツの哲学を基調にしながら、さらに理性的な立場を体系化したのがヴォルフ(C. Wolff, 1679-1754 )である。ところがその理論の体系化過程において、ライプニッツの真の精神が薄れたり歪 曲されたりしたのであり、さらにライプニッツの主要部分が彼の理論体系から抜けていたのである。特にライプニッツのモナド論や予定調和論は歪曲された。カントは、初めはこのヴォルフ学派に属していたが、のちに彼を合理主義的な独断論の代表者として鋭く批判した。ヴォルフは、根本原理から論理的必然性によって導かれる理性的な認識こそ真の認識であるといい、すべての真理は同一律(矛盾律)に基づいて成立すると考えた。彼は、事実に関する経験的認識の存在も認めていたが、理性的認識と経験的認識には何ら関係性はなく、経験的認識は真の認識とはなりえないとした。
このようにして大陸の理性論は事実に関する認識を軽視して、一切を理性によって、合理的に認識しうると考えるようになり、結局、ヴォルフに至って独断論に陥るようになった(8)。