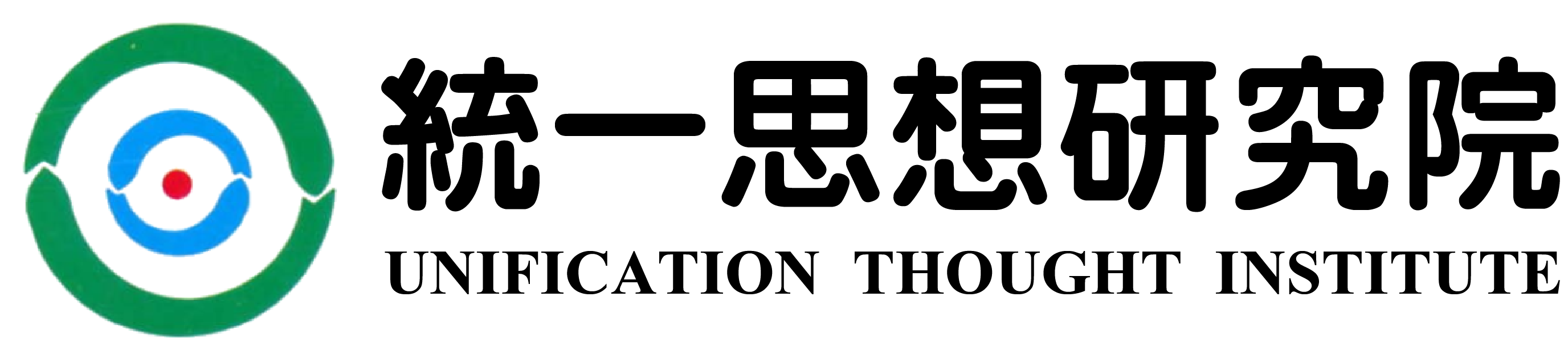(二) 認識の対象の本質
次は、認識の対象の本質をいかなるものと見るかという問題である。認識の対象は主体から独立して客観的に存在するという主張が実在論であり、認識の対象は客観世界にあるのではなくて、主体の意識の中に観念としてのみあるという主張が主観的観念論である。
実在論
実在論には、次のようなものがある。すなわち素朴実在論、科学的実在論、観念実在論(概念実在論)、そして弁証法的唯物論などである。第一の素朴実在論は、自然的実在論ともいうが、物質からなる対象が主観に対して独立にあるという立場であり、われわれの目に見えるとおりに事物が存在するという常識的な見解をいう。言い換えれば、われわれの知覚は対象を正確に模写していると見る立場である。
第二の科学的実在論は、次のようである。すなわち、対象は主観と独立して存在しているが、感性的認識はそのままでは客観的認識とはなりえないとして、感覚を越えた悟性の作用によって、対象から得た経験的事実に科学的な反省を加えることによって、実在を正しく知りうるという見解である。例えば色彩は視覚的現象であるが、科学はこれに科学的批判を加えて、色彩(例えば赤色)は一定の波長をもつ電磁波(光線)に基づいた感覚であると見るのである。また視覚上の稲光りと聴覚上の雷鳴は、科学的には空中で起こる放電現象によるものと見るのである。このように、常識的な実在観に科学的な反省を加えた理論が科学的実在論である。
第三の観念実在論は、客観的観念論ともいう。対象の本質は人間の意識を超えた精神的な客観的なものであるという見解をいう。すなわち精神は人間のみにあるのでなく、人間が出現する前から世界の根源として存在したのであり、この根源的な精神こそ世界の真の実在であり、宇宙の原型であり、万物はその表現にすぎないと見る立場である。例えばプラトンは、事物の本質であるイデアを真なる実在と考え、世界はイデアの影にすぎないと主張した。またヘーゲルは、世界は絶対精神の自己展開であると主張した。
さらに弁証法的唯物論において、対象は意識から独立して存在し、意識に反映される客観的実在と見るために、やはり実在論である。それは事物が鏡に映るように、外部の万物が人間の意識(脳髄)に反映されたものが認識であると見る立場である。しかし反映された内容それ自体が必ずそのままでは真実ではないのであり、実践(検証)によってその真実性が確認されるとき、初めて真実となると見るのであって、それが弁証法的認識論すなわち共産主義認識論である。
主観的観念論
実在論は上述したように、認識の対象が、物体であるか観念であるかにかかわらず、主観と独立して存在すると見るのである。それに対して、認識の対象は人間の意識から独立して存在せず、人間の意識に現れる限りにおいて、その存在が認められるというのが主観的観念論である。バークリがその代表であるが、「実在とは知覚されるということである」(esse is percipi )という命題がその主張をよく表している。また「自我の働きを離れて非我(対象)が存在するかどうかは全くいうことができない」というフィヒテ(J.G. Fichte, 1762-1814 )や、「世界は私の表象である」(Die Welt ist meine Vorstellung )といったショーペンハウアー(A. Schopenhauer, 1788-1860 )も全く同じ立場にある。