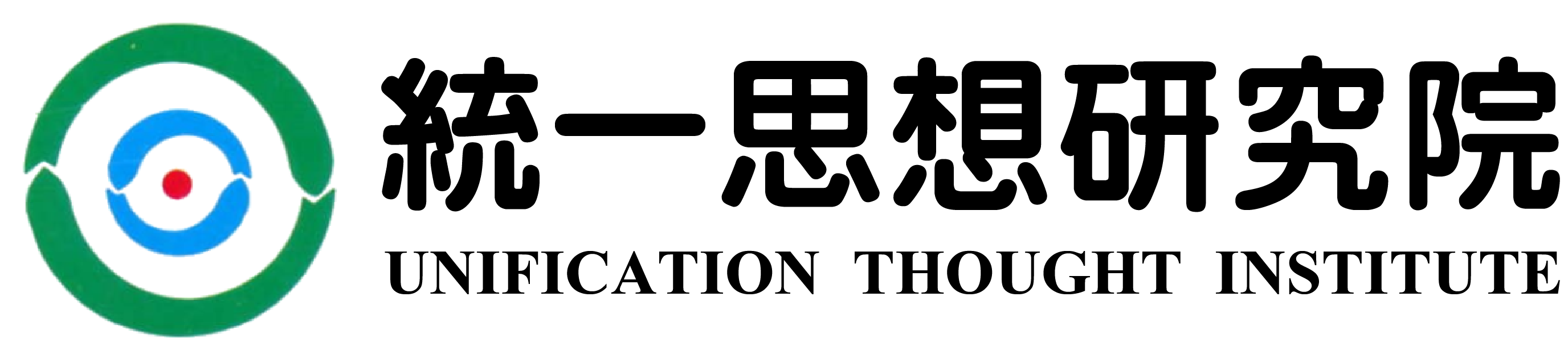(三) 方法から見た認識論
すでに述べたように、認識の起源を経験と見た経験論は懐疑論に陥り、認識の起源を理性にあると見た理性論は独断論に陥った。そのような結果に陥ったのは、経験がいかにして認識になるのか、また理性によっていかに認識が成立するのかという問題、すなわち認識の方法を考察しなかったためである。このような認識の方法を重視し、これを本格的に扱ったのが、カントの先験的方法とヘーゲルやマルクスの弁証法的方法である。ここでは、カントとマルクスの方法について要点を紹介することにする。
(1) カントの先験的方法
英国の経験論は懐疑論に、大陸の合理論は独断論に陥ったが、この二つの立場を総合して新しい見解を立てたのがカント(I. Kant, 1724-1804 )である。経験論は認識の起源を経験であると見て理性の働きを無視することによって、そして理性論は理性を万能なものと見なすことによって、両者共に誤ったとカントは考えた。そこでカントは、正しい認識を得るためには、経験がいかにして認識となりうるかということに対する分析から始めなければならないのであり、そのためには理性の働きの検討すなわち批判をしなければならないと考えた。
カントは『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三つの批判書を著したが、それぞれ真理はいかにして可能であるか、善はいかにして可能であるか、美はいかにして可能であるか、という真善美の価値の実現に関する内容を扱っている。そのうち認識論に関するのが『純粋理性批判』である。
『純粋理性批判』の要点
カントは、知識は経験を通じて増大するという事実と、正しい知識は普遍妥当性をもたなければならないという事実を根拠として、経験論と理性論を統一しようとした。経験によって初めて認識能力が作用することは自明のことであるが、そこにおいてカントが見いだしたのは、認識する主観のうちに先天的な認識の形式(観念)が存在するということであった。すなわち、対象から来る感性的内容(感覚、質料、感覚の多様、感覚的素材ともいう)が主観の先天的形式によって秩序づけられることによって、認識の対象(経験の対象)が成立することであった。従来の経験論や理性論が、いずれも対象を直接的に把握するのに対して、カントは、認識の対象は主観によって構成されるといい、その考え方を「コペルニクス的転回」と自賛した。カントの認識論は、このように対象そのものの認識を目指すものではなくて、客観的真理性はいかにして獲得されるかを明らかにしようとするものであって、これを先験的(超越的ともいう、transzendental )方法と名づけた。
カントによれば、認識は判断である。判断は命題であるが、そこには主語と述語がある。したがって認識を通じて知識が増えるということは、判断(命題)において、主語の概念の中になかった新しい概念が述語の中に含まれていることを意味する。カントはそのような判断を総合判断という。それに対して、主語の概念の中に述語の概念がすでに含まれている判断を分析判断という。結局、総合判断によってのみ新しい知識が得られるのである。
カントが挙げている分析判断と総合判断の例には、次のようなものがある。「物体は延長をもっている」という判断は、物体の概念の中にすでに延長の意味が含まれているから分析判断である。他方、「直線は二点間の最短の線である」という判断は総合判断である。直線という概念は長短という量を含まず、ただまっすぐであるという性質を示しているにすぎないからである。すなわち最短という概念は全く新たに付け加わったものである。
しかし総合判断によって新しい知識を得るとしても、その知識が普遍妥当性をもたなければ、それは正しい知識とはなりえない。知識が普遍妥当性をもつためには、それは単なる経験的認識であってはならず、経験から独立した先天的(アプリオリ)な要素をもたなくてはならない。つまり総合判断が普遍妥当性をもつためには、それは先天的な認識すなわち先天的総合判断でなければならない。そこでカントが取り組んだ問題は、「アプリオリな総合判断はいかにして可能であるか(9)」ということであった。
内容と形式
カントは、内容と形式の統一として、経験論と理性論の総合を成し遂げようとした。内容とは、外界の事物からの刺激によってわれわれの感性に与えられた表象すなわち意識内容をいう。内容は認識の素材(Stoff )または質料(Materie )であって、外来的なものであるから後天的、経験的な要素である。
他方、形式とは質料すなわち感覚の多様を総合・統一する限定性であり、枠組みである。すなわち感性的段階において形成された各種の質料を統一する骨格である。この形式こそ先天的なものであり、その感性的内容に統一性を与える枠である。この先天的形式には二つある。一つは感覚の多様を直観的に時間的・空間的に限定する枠としての直観形式であり、もう一つは悟性の思惟を限定する思惟形式である。このような先天的な形式によって普遍妥当性をもつ総合判断が可能となるというのである。
時間的、空間的概念としての直観形式は、感性的段階において感覚の多様を時間的、空間的にとらえる直感的な形式である。しかし、感性的段階における直観のみでは認識は成立しない。認識が成立するためには、対象が悟性によって思惟される過程が必要である。したがって悟性段階における思惟を限定する枠組みとしての先天的な形式、つまり先天的な概念としての思惟形式が存在すると主張した。つまり、直観形式でとらえた内容と思惟形式(概念)の結合によって、認識が成立するとしたのである。そのことをカントは、「内容なき思惟は空虚であり、概念なき直感は盲目である(10)」という言葉で表現した。
カントは、悟性における先天的な概念(思惟形式)を純粋悟性概念(reiner Verstandesbegriff )またはカテゴリー(範疇、Kategorie )と名づけた。そしてカントは、アリストテレス以来の一般論理学における判断の形式(悟性形式)を整理することによって、次のような十二のカテゴリーを導いた。
1 分量(Quantität)
単一性(Einheit )
数多性(Vielheit )
総体性(Allheit )
2 性質(Qualität)
実在性(Realität )
否定性(Negation )
制限性(Limitation )
3 関係( Relation )
実体性(Substanz )
因果性(Kausalität )
相互性(Gemeinschaft )
4 様相(Modalität )
可能性(Möglichkeit )
現実性(Wirklichkeit )
必然性(Notwendigkeit )
このように、カントは対象の感性的内容が直感形式を通じて直感され、思惟形式(カテゴリー)を通じて思惟されることによって、認識は可能になると主張した。ところで、感性的段階における感性的内容(直観的内容)と悟性的段階における思惟形式は自動的に総合されるものではない。感性と悟性は同じ認識能力の一部分ではあるが、本質的には異質的なものである。ここに、両要素を共有する第三の力が必要である。それが構想力(創造力、Einbildungskraft )であり、この構想力によって直観的内容と思惟形式が統一され、多様な質料の断片が総合、統一されるようになる。
このように感性的段階の直観的内容と悟性的段階の思惟形式が構想力によって総合・統一されてできた構成物が、まさにカントにおける認識の対象である。したがって、カントにおける認識の対象は客観的に外界に実在するものではなく、認識の過程において構成されるのである。
ここでカントの認識の対象は、経験論の後天的要素と理性論の先天的な要素が一つに統一されたものであることが分かる。そのとき、認識するわれわれの意識は経験的な断片的な意識であってはならず、経験的な意識の根底にある統一力をもつ純粋意識でなくてはならない。カントは、それを意識一般(Bewusstsein Überhaupt )とか、純粋統覚(reine Apperzeption )とか、先験的統覚(transzendentale Apperzeption )と呼んだ。さらに、感性と悟性の働きがいかに結びつけられるかということに対しては、すでに述べたように、カントは構想力(Einbildungskraft )がその媒介の役割を果たしているといった。
形而上学の否定と物自体
このようにして、現象世界における認識、すなわち自然科学や数学において、いかにして確実な認識が成立しうるかということを論じたのちに、カントは形而上学が果たして可能であるかどうかを検討した。感性的な内容のない形而上学は、感性的直感の対象になりえず、したがって認識することはできない。ところが人間の理性の働きは、悟性のみに関するのであって感性とは直接関係しないために、現実に存在しないものをあたかも存在しているかのように錯覚する場合がある。そのような錯覚をカントは、先験的仮象(transzendentaler Schein )と名づけた。先験的仮象には、霊魂の理念、宇宙(世界)の理念、および神の理念の三つがある(11)。
そのうち、宇宙の理念すなわち宇宙論的仮象を純粋理性の二律背反(アンチノミー、 Antinomie )と呼んだ。それは理性が無制約者(無限なる宇宙)を追究するとき、同一の論拠から二つの全く相反する結論に到達してしまうことを意味している。例えば「世界は時間における始まりをもち、空間に関しても限界をもつ」(定立)、「世界は時間における始まりをもたず、空間についても限界をもたない」(反定立)という二つの相反する命題がその例である。これは、感性に与えられた内容をそのまま世界全体として把握しようとするところからくる誤りであるとした。
カントは、対象から来る感性的内容が、主観の先天的な形式によって構成される限りにおいて認識が成立するのであって、対象それ自体、すなわち物自体(Ding an sich )は、決して認識することはできないとした。物自体の世界とは、現象的世界の背後にあるとされる世界であり、叡智界ともいう。しかしカントは、物自体の世界を否定し去ったのではなかった。『実践理性批判』において、それは道徳を実現するために要請される世界であるとした。そして叡智界が成立するためには、自由と魂の不死と神の存在が要請されなくてはならないといった。
(2) マルクス主義の認識論
次は、唯物弁証法に基づいた認識論について説明する。唯物弁証法による認識論は、マルクス主義認識論または弁証法的唯物論の認識論といわれる。
反映論(模写説)
唯物弁証法によれば、精神(意識)は脳の産物または機能である(12)。そして、客観的実在が意識に反映する(模写される)ことによって認識がなされると見ている。これを反映論または模写説(teoriya otrazhenia, copy theory)という。そのことをエンゲルスは「われわれは……ふたたび唯物論的にわれわれの頭脳のなかの概念を現実の事物の模写と解した(13)」といい、レーニンは「人間の意識は(人間の意識が存在している場合に)それから独立して存在しておりかつ発展している外界を反映する(14)」といった。
マルクス主義認識論においては、カントのいう感性的内容がそのまま客観的実在の意識への反映であるのみならず、思惟形式も客観世界の実在形式の意識への反映であると見ている。
感性的認識、理性的認識、実践
認識は、単に客観世界の反映ではない。反映された内容は必ず実践を通じて検証されなくてはならない。レーニンはその過程を次のように説明している。「生き生きとした直観から抽象的思考へ、そしてこれから実践へ——これが真理の認識の、すなわち、客観実在の認識の、弁証法な道すじである(15)」。
唯物弁証法的認識の過程をさらに具体的に説明したのが毛沢東である。彼は、次のように述べている。
認識は実践にもとづいて浅いものから深いものへとすすむというのが、認識の発展過程に関する弁証法的唯物論の理論である。……すなわち認識は低い段階では感性的なものとしてあらわれ、高い段階では論理的なものとしてあらわれるが、いずれの段階も一つの統一的な認識過程のなかの段階である。感性と理性という二つのものの性質はちがっているが、だからといって、それらはたがいに切りはなされたものでなく、実践の基礎のうえで統一されているのである(16)。
認識の過程の第一歩は、外界の事物に接触しはじめることであって、それは感覚の段階である[感性的認識の段階]。第二歩は、感覚された材料を綜合して、整理し改造することであって、それは概念、判断および推理の段階である[理性的認識の段階(17)]。
このように認識は、感性的認識から理性的認識(または論理的認識)へ、理性的認識から実践へと進んでいくのである。ところで、認識と実践は一回きりのものではない。「実践、認識、再実践、再認識という形式が循環往復して、無限にくりかえされ、そして各循環ごとに実践と認識の内容が一段と高い段階にすすむ(18)」のである。
カントは、主観が対象を構成する限りにおいて認識がなされるのであり、現象の背後にある「物自体」は認識不可能であるといって、不可知論を主張した。それに対してマルクス主義は、現象を通じてのみ事物の本質は認識されるのであり、実践によって事実を完全に認識できると主張し、現象から離れた「物自体」の存在を否定したのである。エンゲルスは、カントに反論して次のようにいっている。
カントの時代には自然の物体に関するわれわれの知識は、極めて断片的であったので、カントもその自然物についてわれわれの僅かな知識の背後に何かまだ神秘な「物自体」があるかもしれぬといったのであろう。だが、科学のすばらしい進歩によってこれらのわかりにくかったものがつぎつぎに把握され、分析されたのである。それどころか、再生産(reproduce)されるまでになったのだ。いやしくも、われわれが作りうるものを、われわれが認識しえないとは考えられない(19)。
ところで認識と実践の過程において、実践がより重要であるという。すなわち毛沢東は「弁証法的唯物論の認識論は、実践を第一の地位におき、人間の認識は少しも実践からはなれることはできない(20)」というのである。そして実践というとき、一般的には人間の自然に対する働きかけや、人間のいろいろな社会活動をいうが、マルクス主義の場合、その中でも革命を最高の実践であると見ている。したがって、認識の最終的な目的は革命にあるといえる。実際、毛沢東は次のように述べている。「認識の能動的作用は、感性的認識から理性的認識への能動的な飛躍にあらわれるばかりでない。もっと重要なことは、それがさらに理性的認識から革命的実践へという飛躍にもあらわれなければならないということである(21)」。
ここで、論理的認識(理性的認識)における思惟形式について述べる。論理的認識は概念を媒介とした判断、推理などの思惟活動をいうが、そのとき、思惟形式が重要な役割を果たしている。反映論を主張するマルクス主義は、思惟形式は客観世界における諸過程の意識への反映、すなわち存在形式の意識への反映であると見ている。マルクス主義におけるカテゴリー(実在形式・思惟形式)には次のようなものがある(22)。
物質 限度
運動 矛盾
空間 個別と普遍
時間 原因と結果
意識 必然性と偶然性
有限と無限 可能性と現実性
量 内容と形式
質 本質と現象
絶対的真理と相対的真理
認識と実践の反復によって知識が発展していくのであるが、知識の発展とは、知識の内容が豊富になることと、知識の正確度がいっそう高くなることを意味する。したがってここに、知識(真理)の相対性と絶対性が問題になるのである。
マルクス主義は、客観的実在を正確に反映したものが真理であるという。すなわち、「われわれの感覚、知覚、表象、概念、理論が客観世界に一致し、それを正しく反映するならば、それらのものは真であるという。また真なる言明、判断または理論を真理とよぶ(23)」といっている。
さらにマルクス主義は、実践——結局は革命的実践——が真理の基準であると主張する。すなわち認識が真であるかどうかは、実践を通じて現実と比較し、認識が現実に一致しているかどうかを確かめればよいというのである。このことをマルクスは「実践のうちで人間はその思考の真理を、言いかえれば、その思考の現実性と力、此岸性を証明しなければならない(24)」といい、毛沢東は「マルクス主義者は、人々の社会的実践だけが、外界について人々の認識が真理であるかどうかの基準であると考える(25)」といった。結局、革命的実践が真理の基準であるということになるのである。
ところで、ある特定の時代の知識は部分的、不完全であって相対的真理にとどまるが、科学の発展によって知識は、完全な絶対的真理に限りなく近づくといい、絶対的真理の存在を承認する。それゆえ「相対的真理と絶対的真理のあいだにはこえがたい境界は存在しない(26)」とレーニンはいう。そしてまた相対的な真理の中に絶対的に真なる内容が含まれていて、それが不断に蓄積されたとき、絶対的真理になるというのである(27)。
以上で「従来の認識論」の項目をすべて終える。初めに述べたように、以上は従来の認識論の要点を参考として紹介しただけである。