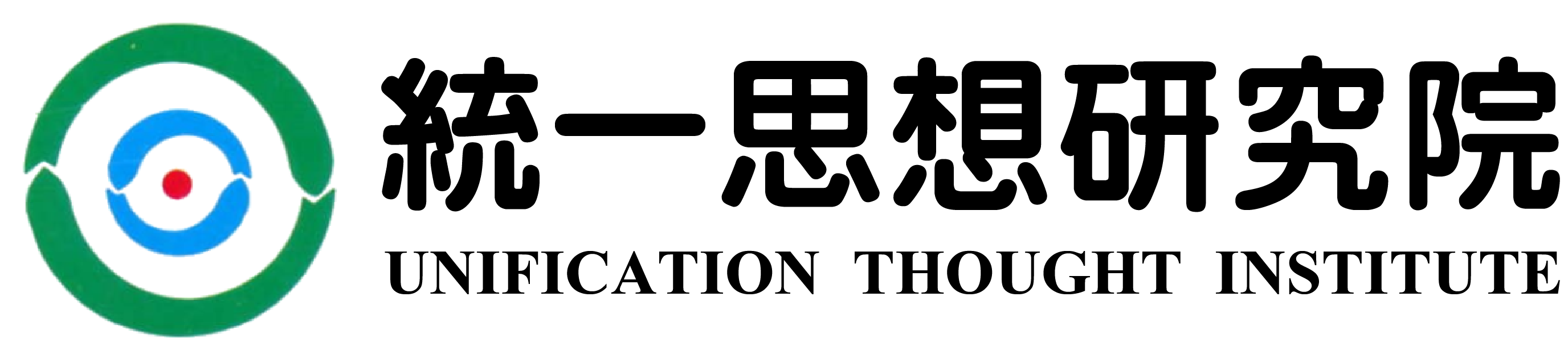(六) 認識過程と身体的条件
統一認識論は統一原理または統一思想を根拠とした認識論であるから、従来の認識論と異なる点があるのは当然である。ところで統一認識論の主張が科学的見解に反するとか、それと距離があるとしたら、統一認識論も過去の認識論と同じく、主唱者の単なる主張として終わり、普遍妥当性は認められないであろう。
従来の認識論、すなわち経験論も、理性論も、カントの先験的認識論も、マルクス主義認識論も、みな科学的な見解と無関係な理論であったか、または今日の科学的見解と合わなくなっている。したがって、科学の発達している今日において、それらはほとんど説得力をもつことができない。ところが、統一認識論は科学的な立場から見ても妥当な理論であるといえる。そのことを以下に論じることにする。
心理作用と生理作用の並行性
統一思想は、二性性相である原相に似せて万物は創造されたという理論に基づいて、すべての存在は性相と形状の二性性相として存在することを主張する。人間は心と体の二重的存在であるが、人体を構成している細胞、組織、器官なども、すべて心的要素と物質的要素の統一体なのである。そればかりでなく、人間のあらゆる活動や作用も二重的であって、そこには必ず心理作用と生理作用が統一的に並行して行われているのである。したがって統一思想から見れば、認識作用においても、必ず心理的過程と生理的過程が並行しているのである。例えば、心と脳の授受作用によって精神作用(意識作用)が現れるのである(図9—7)。ここにおいて、心とは生心(霊人体の心)と肉心(肉身の心)の合性体である。
脳の研究の世界的権威であるペンフィールド(W. Penfield, 1891-1976 )は、脳をコンピュータにたとえ、「脳はコンピュータ、心はプログラマー」であると述べた(34)。同じく著名な脳の研究者であるエックルス(J.C. Eccles, 1903-97 )も、心と脳は別のものであり、心と脳の相互作用として心身問題をとらえなくてはならないといった(35)。彼らの主張は、心と脳の授受作用によって精神作用が営まれるという統一思想の見解と一致するものである。これは、統一認識論の主張が科学的見解と一致する実例の一つとなるのである。
原意識、原映像の対応源
次に、統一認識論における独特な概念である原意識と原映像に対して、それを裏づける科学者の見解を見てみよう。
すでに説明したように、原意識は細胞や組織に浸み込んだ宇宙意識または生命であり、原映像はこの意識のフィルムに写された映像である。ここに原意識は目的意識であり、原映像は情報にほかならない。これは細胞が目的意識をもちながら、情報に基づいて一定の機能を果たすことを意味している。
ここで、サイバネティックスの理論によって原意識と原映像を検証してみよう。サイバネティックスとは、機械における情報の伝達と制御の自動化方式に関する科学のことをいう。生物においては、情報が感覚器官を通じて中枢に伝達され、中枢がそれを統合して適切な指令を末 梢神経を通じて効果器(筋肉)に送るが、この現象は自動機械の自動操作と同じようなものなので、生物におけるサイバネティックス現象と呼ばれる。しかし生物の場合、その自動現象は文字どおりの自動操作ではなく、生物がもっている自律性による自律的な操作である。
このようなサイバネティックスの現象は、一個の細胞においても見られる。すなわち、細胞質から核への情報の伝達とこれに対する核の反応が絶えず自律的に繰り返されながら、細胞の生存、増殖などが営まれている。このようなサイバネティックスの現象を通じて、一個の細胞においても自律性があることを見いだすことができる。この細胞における自律性こそ、生命であり、原意識にほかならない。
例えばフランスの生理学者、アンドレ・グド=ペロ(Andrée Goudot-Perrot )は、その著『生物のサイバネティックス』の中で次のように説明している。細胞の情報源をもっている細胞核が細胞質の小器官(ミトコンドリア、ゴルジ体など)に命令を与えて、細胞の生活に必要な化学反応を行っている(36)。ここに細胞の情報とは、生物の解剖学的形態および本質的機能に関する一切の情報をいうのである(37)。
ここに、次のような疑問が当然生じてくる。第一に、情報は解読され記憶されなければならないが、その解読と記憶の主体は何かということである。第二に、細胞の生活に必要な化学反応を起こすために、細胞核が命令を発しようとすれば、細胞核は細胞内部の状況を正確に覚知していなければならないが、その覚知の主体は何かということである。
それに対して現象面のみを扱っている科学(生理学)の立場からは答えることができない。しかし二性性相の理論をもつ統一思想は、そこに性相として合目的な要素すなわち意識が作用していることを明言することができる。細胞の中にあるこの意識がまさに原意識であり、情報が原映像なのである。
認識の三段階の対応源
以上、認識における三段階である感性的段階、悟性的段階、理性的段階について説明した。ところで今日の大脳生理学において、大脳皮質にこのような認識の三段階に対応する生理過程があると考えられている。
大脳皮質は大きく分けて、感覚器からの信号を受け取る感覚野、随意運動に関係する信号を送り出す運動野、そしてそれ以外の連合野に分けられる。連合野は前頭連合野、頭頂連合野、側頭連合野に分けられる。前頭連合野は意志、創造、思考などの機能にかかわり、頭頂連合野は知覚、判断、理解などの機能にかかわり、側頭連合野は記憶のメカニズムに関係していると考えられている。
まず、光、音、味、香り、触覚などの情報が、末梢神経を通じて、それぞれ視覚、聴覚、味覚、嗅覚、皮膚感覚(体性感覚)などの感覚野に伝わる。感覚野における生理的過程が感性的段階の認識に対応するものである。次に、感覚野の情報は頭頂連合野に集められて、そこで知覚され、判断(理解)されるのであるが、これが悟性的段階の認識に対応する生理的過程である。そして、この理解、判断に基づいて前頭連合野において思考がなされ、創造活動が行われるのであるが、これが理性的段階の認識に対応する過程である。このように三段階の認識には、それぞれ大脳の生理的な過程が対応しているのである。これを図で表すと、図9—8のようになる(38)。
情報伝達における心理的過程と生理的過程の対応関係
人体において、絶えず体の外部や内部から様々な情報を受け入れて、それを処理し、それに対応する働きがなされている。目、耳、皮膚などの受容器(感覚器)が受け入れた刺激は、インパルスとなって神経線維の求心路を通って中枢神経に至る。中枢神経はその情報を処理して指令を送るのであるが、その指令がインパルスとして神経線維の遠心路を通って、筋肉、分泌腺などの効果器に伝達されて反応を生じさせるのである(図9—9)。
ある刺激を受けたとき、無意識のうちに、すなわち上位中枢とは無関係に反応が起きる場合を反射という。その場合、脊髄、延髄、中脳などが、その反射中枢となって、刺激に対して適切な指令を送っているのである。
では受容器を通じて入った情報は、いかにして伝わるのであろうか。受容器に入った情報は、神経細胞において電気的な神経インパルスに変わる。神経インパルスとは、神経線維の興奮部と興奮していない部分との間の膜電位の変動をいうが、それが神経線維に沿って移動するのである。そのとき生じる電位の変化を活動電位という。神経線維の膜は静止状態において内部が負に帯電しているが、インパルスが通過するとき、荷電が逆転して、内側が正に帯電する。これは、ナトリウムイオンが内側に流れ込むことによって起こる現象である。次いで、カリウムイオンが外側に流れ出ることによって荷電はもとの状態を回復する。このようにして膜電位の変動が起り、それが移動していくのである(図9—10)。
次に、神経細胞の連結部、すなわちシナプスでは神経インパルスはいかにして伝達されるのであろうか。シナプスは体液が入っている空間であるが、電気的なインパルスがシナプスに至り、化学的な伝達物質に変換されて、シナプスの間隙を移動する。そしてその化学物質が次の神経線維に達すれば、そこで再び電気的インパルスに変換される。すなわち、一つの神経細胞の神経線維を流れる電気的な信号が、シナプスでは化学的な信号(化学物質)に変わり、この化学的信号が次の神経細胞の神経線維に達すると、再び電気的な信号に変わるのである。シナプスにおける神経伝達物質は、電気インパルスが流れる神経が運動神経や副交感神経の場合はアセチルコリンであり、交感神経の場合はノルアドレナリンであるといわれている。以上説明した情報伝達のメカニズムを図で表せば、図9—11のようになる。
以上が情報伝達に対する生理的過程であるが、統一思想から見れば、この生理的過程の背後に必ず意識過程が存在しているのである。すなわち神経線維における活動電位や、シナプスにおける化学物質の移動の背後において、原意識が作用しており、原意識の情報の内容を覚知しながら情報を中枢へ伝達していると見るのである。言い換えれば、原意識を情報の伝達者と見なすことができる。それで神経線維における活動電位やシナプスにおける化学物質の出現は、情報の伝達者である原意識によって起こる物理的現象と見るのである。
原型の形成における対応関係
先に原映像と関係像の対応源が、それぞれ細胞や組織の内容と、諸要素の相互関係であることを明らかにしたが、それらをそれぞれ末端原映像と末端関係像と呼ぶことにする。それに対して、認識の悟性的段階において現れる原映像と関係像を中枢原映像と中枢関係像と呼ぶことにする。
末端原映像が神経路を通じて上位中枢に至る過程において、中枢神経系の各位において選別され、さらに複合、連合されて中枢原映像となるのである。末端関係像の場合も、中枢神経系の各位において選別され、さらに複合、連合されて中枢関係像となるが、それが大脳皮質に至って思惟形式となるのである。なお、その際、中枢神経系の各位は、それぞれがその位置における原映像と関係像を保管しているのである。
認識の原型を構成しているものには、このような原映像と思惟形式のほかに経験的映像または経験的観念と呼ばれるものがある。それは、それまでの経験において得られた映像(観念)が、記憶中枢に保管されているものであって、それもその後の認識において原型の一部になるのである。そのとき、すでに述べたように、原映像と思惟形式を「先天的原型」(または「原初的原型」)といい、経験的映像を「経験的原型」というのである。
中枢神経系において、情報が下位から上位へと移行するにしたがって、情報の受容量(入力)と放出量(出力)が増大すると同時に、情報の処理の仕方は、よりいっそう包括化され普遍化される。これは、一国の行政において、行政組織が上位になるにしたがって、扱う情報量が増大し、情報の処理方式もより包括的、普遍的になるのと同じである。
最も上位の中枢すなわち大脳皮質において、情報の受容はとりもなおさず認識であり、情報の保管は記憶であり、情報の放出は構想(思考)と創造と実践である。このような大脳皮質の統合作用とは次元が異なるけれども、下位中枢の統合作用も、その方式は大脳皮質の場合と同様であって、意識による合目的的な統合作用がそれぞれの中枢において行われているのである。合目的的な統合作用とは、生理的統合作用と意識的(精神的)統合作用の統一をいう。つまり、中枢神経系の各位において、生理的な統合作用と意識的な統合作用が並行して統一的に行われているのである。したがって、中枢神経の情報(神経インパルス)の伝達という生理過程には、必ず、判断、記憶、構想などの心理過程が対応しているのである。
関係像(形式像)の伝達という観点から見るとき、下位の中枢から上位の中枢に移行するにしたがって多様な情報が処理されて次第に単純化されるが、これは末端の個別的な関係像が上位に移るにしたがって次第に普遍化され一般化されることを意味する。そして大脳皮質に至ると、完全に概念化されて思惟形式すなわち範 疇となるのである。これは、あたかも行政施策が行政組織の末端に行くほど、より個別性、特殊性を帯びるようになり、中央に行くほど、一般性、普遍性を帯びるようになるのと同じである。
原型と生理学
原型とは、認識に際して主体があらかじめもっている観念や概念をいうが、これを別の言葉で記憶ということができる。先に、人間は先天的な原型と経験的な原型をもっていることを説明したが、それらは生理学者の表現を借りれば、「遺伝的記憶」と経験による「獲得した記憶」に相当するといえる(39)。
生物体としての人間の細胞や組織に関する情報である「遺伝的記憶」は大脳辺縁系——大脳の、新皮質に包み込まれている古い皮質からなる部分——などに蓄えられていると大脳生理学は見ている。それでは「獲得した記憶」が医学的に見て、いかにしてどこに蓄えられているのであろうか。
記憶には、数秒間持続する短期の記憶と、数時間から数年間にわたって持続する長期の記憶がある。短期の記憶は、電気的な反復回路に基づいているとされている。一方、長期の記憶に対しては「ニューロン回路説」と「記憶物質説」の二つの説が唱えられてきた。ニューロン回路説は、個々の記憶は接合部(シナプス)に変化がもたらされた特殊なニューロンの回路網に蓄えられるという立場であり、記憶物質説は個々の記憶に対して、RNAやペプチドなどの記憶物質が関係していると見る立場である。しかし最近では、記憶物質説を主張する研究者は少なくなっている(40)。
長期の記憶の座に関しては、次のように考えられている。大脳の内部の大脳辺縁系には海馬と呼ばれる部分がある。この海馬が情報の記憶の役割を果たし、その後、記憶は大脳新皮質(側頭葉)に永続的に蓄えられるとされている(41)。すなわち記憶は、海馬を通じて側頭葉に蓄えられると見ているのである。
認識に際して、このような記憶(蓄積されている知識)が、感覚器官を通じて入ってきた外界からの対象の情報と照合され、判断されるということを、アンドレ・グド=ペロ(Andrée Goudot-Perrot )は次のように述べている。「感覚受容器によって受けとられる情報——これらの情報は、大脳皮質感覚中枢によって獲得され《記憶》のなかに貯蓄されている知識と照合され、判断される(42)」。これは、外界から入ってきた情報(外的映像)が原型(内的映像)と照合されて一致・不一致が判断されることが認識であるという統一認識論の主張と、軌を一にする見解である(43)。
観念の記号化と記号の観念化
最後に、記号の観念化と観念の記号化について述べる。主体である人間が対象を認識するとき、対象の情報が感覚器に達すれば、それはインパルスとなって感覚神経を伝わって上位中枢に達し、大脳皮質の感覚中枢において、インパルス(一種の記号)は観念化されて、意識の鏡に一定の映像(観念)として映る。これは「記号の観念化」である。それに対して実践の場合、ある一定の観念に基づいて行動がなされるが、そのとき観念がインパルスとなって運動神経を伝わっていき効果器(筋肉)を動かす。インパルスは一種の記号であるから、これは「観念の記号化」である。
今日の大脳生理学によれば、認識において生じた観念が、記憶として脳の一定の場所に貯蓄されるとき、その観念はニューロンの特殊な結合の様式として記号化され、またその記号化された記憶が必要に応じて想起されるとき、意識は記号を解読して観念として理解するという。これは記憶の貯蔵と想起においても「観念の記号化」と「記号の観念化」が行われていることを意味する。例えば、大脳生理学者ガザニガ(M.S. Gazzaniga )とレドゥー(J.E. LeDoux )は次のように述べている。
我々の経験は非常に多くの特徴を持っているから、経験の個々の特徴が脳の中でそれぞれ特異的に符号化されるとみなされる(44)。
記憶の貯蔵と符号化および符号の解読が多面的な過程で、脳の中で多重的につかさどられているという事実は今後もっと明らかにされるであろう(45)。
このような「観念」と「記号」の相互の転換は、あたかも一次コイルと二次コイルの間を誘導によって電流が移動するように、「観念」を担っている性相的な心的コイルと、「記号」を担っている形状的な物質的コイル(ニューロン)との間に生じる、一種の誘導現象であると見なすことができる。「観念」と「記号」の相互転換は、認識作用が心的過程と生理的過程の授受作用によって営まれていることを裏づけるものである。