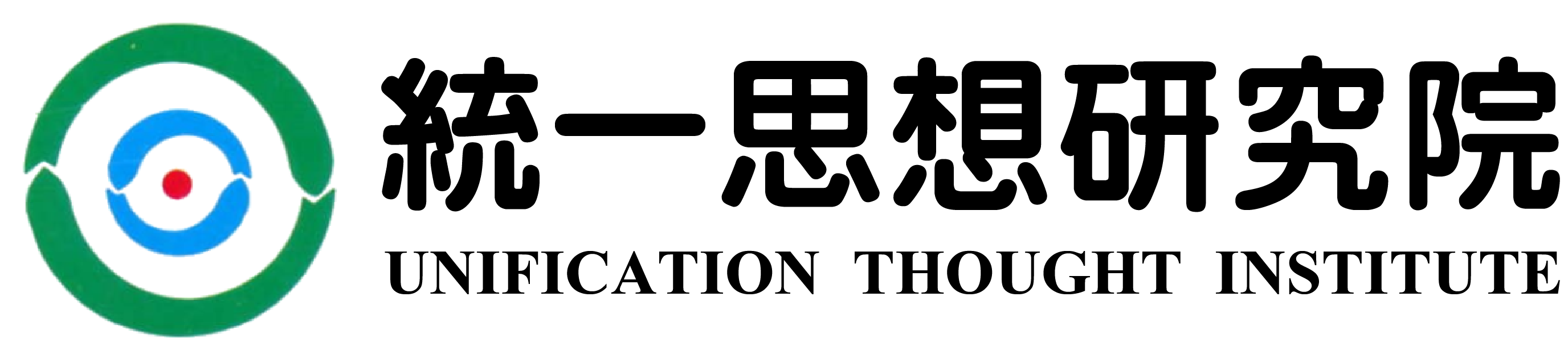(二) マルクス主義認識論の批判
反映論への批判
すでに述べたように、いくら外界が意識に反映したとしても、判断の基準(尺度)として、認識主体の中に外界の事物に対応する原型がなければ認識は成立しえない。さらに認識は主体と対象の授受作用によってなされるから、主体が対象に対して関心をもつことが必要である。外界の対象が主体の意識に反映したとしても、主体が対象に関心をもたなければ認識は成立しないからである。すなわち反映というような受動的な物質的過程だけでは認識は成立せず、積極的な心的過程(対象への関心や照合の機能)が関与することによって、初めて認識は可能となるのである。
感性的認識、理性的認識、実践への批判
マルクス主義認識論では、認識過程は感性的認識、理性的認識(論理的認識)、そして実践(革命的実践)の三段階よりなっている。
ここでまず問題となるのは、脳の産物あるいは機能であり、客観的実在を反映するという意識が、いかにして論理的な認識(抽象、判断、推理)などを行いうるか、またいかにして実践を指令しうるかということである。外界を反映する受動的な過程と、論理的な認識や能動的な実践の過程との間には、非常に大きなギャップがあるにもかかわらず、これについては何ら合理的な説明がなされていない。すなわち、論理が飛躍しているのである。
統一思想から見るとき、論理的な認識や実践は、脳における生理的過程のみでは決して説明されない。認識作用は、心(精神)と脳の授受作用によってなされるからである。すなわち論理的な認識や実践は、悟性や理性の働きをもつ心と、脳が授受作用することによってなされるのである。
次に問題になるのは、認識における実践の役割である。レーニンは認識は実践へ移行するといい、毛沢東は認識と実践の不可分性を主張しているが、その点に関しては統一思想は何ら異論はない。万物は人間の喜びの対象として創造されたのであり、人間は創造目的に従って万物を主管(実践)するようになっている。したがって人間は、主管のために万物を認識するのである。認識と実践は、人間と万物の授受作用の相対的な回路をなしているのであり(図9—12)、実践(主管)を離れた認識はなく、認識を離れた実践(主管)もないのである。
ところでマルクス主義の主張する実践とは、最終的には革命を目標とするものであった。それに対して統一思想は、認識と実践は、革命を目的としてなされるものでは決してなく、創造目的の実現のためになされなくてはならないことを主張する。創造目的の実現とは、神は人間を愛することによって喜ばれ、人間は万物を愛で主管し、喜びを得るような世界を実現することである。それゆえ認識も実践も、愛を通じて喜びを実現するために行われるのである。
絶対的真理と相対的真理に対する批判
レーニンと毛沢東は、絶対的真理の存在を承認し、人間は認識と実践を繰り返すことによって絶対的真理に限りなく近づくといった。しかし、彼らのいう絶対的真理における「絶対」の概念は曖昧である。レーニンは、相対的真理の総和が絶対的真理であるという。しかし、相対的真理をいくら総和しても、それは総和された相対的真理であるのみであって、絶対的な真理とはなりえない。
絶対的真理とは、普遍的でありながら、永遠性をもっている真理をいう。したがって、絶対者を基準としなければ絶対の概念が成立しない。絶対的真理は、価値論で説明したように、神の絶対的愛と表裏一体になっている。あたかも太陽の光の暖かさと明るさが表裏一体であって分けられないのと同じである。したがって、神の絶対的な愛を離れて絶対的真理はありえないのである。ゆえに神の愛を中心とするとき、人間は初めて万物の創造目的を理解し、万物に関する真なる知識を得るようになるのである。したがって、神を否定して、いくら実践したとしても、絶対的真理が得られるわけはないのである。