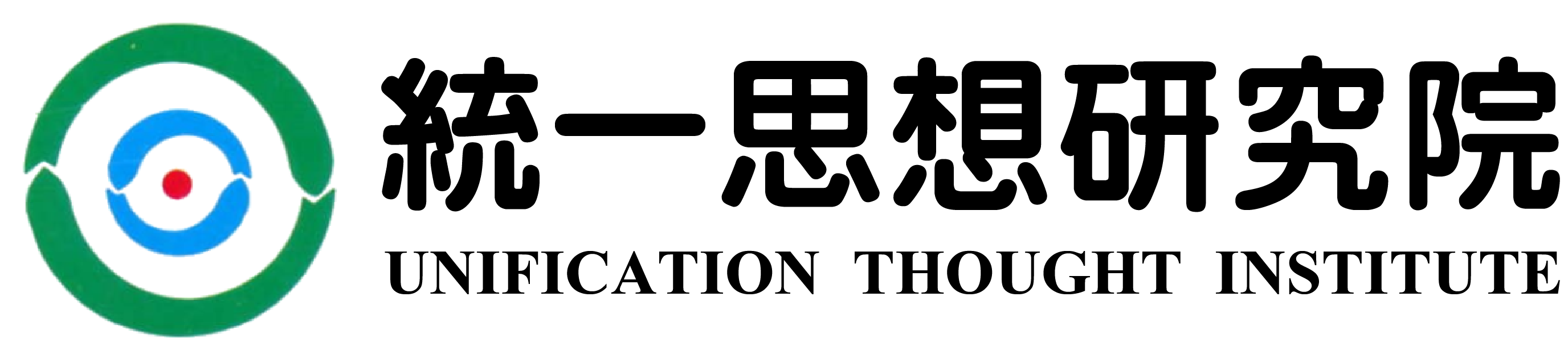(一) 形式論理学
形式論理学は、アリストテレスによって立てられた論理学として、純粋に、思考(判断や推理)の法則や形式のみを研究する学問であり、判断や推理の対象(内容)は一切取り扱っていない。カントは、「ところで論理学が、かかる確実な道をずっと古い時代から歩んできたことは、この学がアリストテレス以来、いささかも後退する必要がなかったところから見ても明白である。……更に論理学について奇異なことは、この学が今日に至るまでいささかも進歩を遂げ得ず、従って打ち見たところそれ自体としてはすでに自己完了している観があるという事実である(1)」(『純粋理性批判』第二版序文)といっている。形式論理学はアリストテレス以来、約二千年間、ほとんど変更なく継続してきたものである。それは、この論理学が思考に関する限り、それなりの客観的な真理を含んでいるからである。統一論理学を紹介するにあたって、まず形式論理学を紹介するのは、この論理学のどの部分が真理であるかを明らかにすると同時に、不十分な点も指摘するためである。以下、形式論理学の要点を紹介する。
(1) 思考の原理
形式論理学は思考の法則として、次の四つの原理を挙げている。
① 同一律(law of identity )
② 矛盾律(law of contradiction)
③ 排中律(law of excluded middle)
④ 充足理由律(law of sufficient reason)
同一律は、「AはAである」という形式で表される。例えば「花は花である」というのがそれである。これは現象の変化にもかかわらず、花であるという事実それ自体は不変であるということを意味している。また思考そのものの一致性をも意味する。すなわち「花」という概念は、いかなる場合にも、同一の意味を有しているということである。さらに「鳥は動物である」というように、二つの概念(鳥と動物)が一致していることをも意味する場合もある。
矛盾律は「Aは非Aではない」という形式で表されるが、これは同一律を裏返したものである。「これは非花ではない」というのは「これは花である」というのと同じ意味であり、「鳥は非動物ではない」というのも「鳥は動物である」というのと同じである。一方は肯定的な表現であり、他方は否定的な表現であるが、内容は同じである。
排中律は、「AはBか非Bのいずれかである」と表される。その意味は、Bと非Bという二つの矛盾する主張の間に、第三の主張はありえないということである。
充足理由律は、ライプニッツによって初めて説かれたものであるが、「すべての思考は必ずしかるべき理由があって存在する」ということである。これを一般的にいえば、「すべて存在するものはその存在の十分な理由を有する」という因果律になる。ところで、この理由には二つの意味がある。一つは根拠(論拠)を意味し、もう一つは原因を意味する。根拠は帰結に対する相対的な概念であり、原因は結果に対する相対的概念である。したがってこの法則は、思考には必ずその論拠があり、存在には必ずその原因があるということを意味するのである。
そのほかいろいろな法則(原理)があるが、それらはみな、この四つの根本原理から演繹されてくるものである。形式論理学は、また三つの根本的な要素(思想の三要素)——概念(concept )、判断(judgment )、推理(inference )——から成り立っている。次にそのことについて説明する。
(2) 概 念
概念とは、事物の本質的な特徴をとらえた一般的な表 象(または考え)をいうが、概念には「内包」(intension )と「外延」(extension )という二つの側面がある。内包は各概念に共通な性質をいい、外延はその概念が適用される対象の範囲をいう。それについて、生物の例を取って説明してみよう。
生物は、動物、脊椎動物、哺乳類、霊長類、人類というように、いろいろな段階の概念に分類される。生物は生命のあるものである。動物にはもちろん生命があるが、その上に感覚器官がある。脊椎動物には、それに加えて脊椎がある。哺乳類には、それに加えて哺乳をするという性質がある。霊長類は、それに加えて物を握る能力をもっている。人類は、さらに理性がある。そのように、それぞれの概念を代表する各段階の生物は共通な性質をもっているが、ある概念のそのような共通な性質のことを、その概念の内包というのである。
生物には動物と植物があり、動物には軟体動物、節足動物、脊椎動物などがあり、脊椎動物には爬虫類、鳥類、哺乳類などがあり、哺乳類には霊長類とか食肉類などがあり、霊長類にはいろいろなサルと人類がいる。以上、ある概念が適用される対象の範囲について述べた。そのような範囲をその概念の外延と呼ぶが、それを図で表せば、図10—1のようになる。
ある二つの概念を比較するとき、外延がより狭く、内包がより広い概念を「種概念」(下位概念)といい、外延がより広く、内包がより狭いものを「類概念」(上位概念)という。たとえば脊椎動物と爬虫類、鳥類、哺乳類などの概念を比べれば、前者は類概念であり、後者は種概念である。また動物という概念と軟体動物、節足動物、脊椎動物などの概念を比べれば、前者が類概念で後者が種概念となる。さらに生物という概念と動物や植物の概念を比べれば、前者が類概念、後者が種概念となる。このような操作を何度も繰り返していくと、それ以上さかのぼれない最高の類概念に至るが、それを範疇(カテゴリー、Kategorie)という(図10—2)。
また先天的に理性に備わっている、経験によらない純粋概念も、やはり範疇と呼ばれている。範疇は学者によって異なっている。なぜかというと、それぞれの学者の思想体系において、最も重要な基本的な概念のことを範疇と呼んでいる場合が多いからである。
初めて範疇を定めたのはアリストテレスであるが、彼は文法を手がかりとして、次のような十個の範疇を立てた。
① 実体(substance )
② 量 (quantity)
③ 質 (quality )
④ 関係(relation)
⑤ 場所(place )
⑥ 時間(time)
⑦ 位置(position)
⑧ 状態(condition )
⑨ 能動(action)
⑩ 被動(passivity )
近世に至り、カントは十二個(四綱十二目)の範 疇を立てたが、それらはカントの十二の判断形式(後述)から導き出したものであった。カントの範疇については、すでに認識論において紹介したとおりである。
(3) 判 断
判断とは何か
判断(judgment)とは、ある対象について、あることを主張することであるが、それは二つの概念の一致あるいは不一致の区別を断定することをいう。それを言語で表現したものが命題(proposition )である。
判断は「主語概念」(主辞、主語、subject )、「述語概念」(賓辞、述語、predicate )、および「繋辞」(連結辞、copula)の三要素から成っている。思考の対象となっている事物が主語概念であり、その内容を規定するのが述語概念であり、これら二つの概念を連結するのが繋辞である。一般的に、主語概念をS、述語概念をP、繋辞を—で表して、判断はS—Pと定式化される。
判断の種類
判断の種類としては、カントの十二の判断形式(四綱十二形式)があるが、それが今日の形式論理学において、そのまま用いられている。カントの十二の判断形式とは、分量、性質、関係、様相の四綱をそれぞれ三つに分けたもので、次のようである。
分量(Quantität )
全称判断(allgemeine Urteil )…すべてのSはPである。
特称判断(besondere Urteil)……若干のSはPである。
単称判断(einzelne Urteil )……このSはPである。
性質(Qualität )
肯定判断(bejahende Urteil)……SはPである。
否定判断(verneinde Urteil)……SはPでない。
無限判断(unendliche Urteil )…Sは非Pである。
関係(Relation )
定言判断(kategorische Urteil )…SはPである。
仮言判断(hypothetische Urteil)…AがBならばCはDである。
選言判断(disjunktive Urteil)……AはBであるかCである。
様相(Modalität )
蓋然判断(problematische Urteil )……SはPであろう。
実然判断(assertorische Urteil)……SはPである。
必然判断(apodiktische Urteil )…SはPでなければならない。
上記のように、カントは四個の分量、性質、関係、様相の綱目において、それぞれを三つに分けたのである。われわれは日常生活において、様々な事件や状況に直面する。そしてそれらに対処するためにいろいろな方案を考える。そうした思考の内容は、人によって千差万別であるのはいうまでもない。しかし、判断に関する限り、上述の四つの綱目の形式に従ってなされているのである。すなわち分量(多いか、少ないか)に関する判断と、性質(…であるか、否か)に関する判断と、概念の相互関係に関する判断と、それから様相(確実性はどうであるか)に関する判断である。
基本的形式
以上の判断形式のうち最も基本となるものが定言判断であるが、それに全称と特称の、量に関する判断形式と、肯定と否定の、質に関する判断形式を組み合わせれば、次の四種の判断が得られる。
全称肯定判断……すべてのSはPである(A)
全称否定判断……すべてのSはPでない(E)
特称肯定判断……あるSはPである(I)
特称否定判断……あるSはPでない(O)
ところで上記の十二の判断形式の中の選言判断と仮言判断を除けば、残りはすべて定言判断に直すことができる。そこでこの定言判断を質と量の立場から分類すれば、仮言判断、選言判断以外の形式はすべて以上の四つの形式(AEIO)に収 斂されるようになる。それでこの四つのAEIOの形式を「判断の基本的形式」という。A、E、I、Oの記号は、ラテン語の affirmo(肯定)とnego(否定)のそれぞれの初めの二つの母音からとったものである。
周延と不周延
定言判断において、その判断が誤謬に陥らないためには、主語と述語の外延の関係が検討されなくてはならない。ある判断において、概念が対象の全範囲にわたって適用される場合もあれば、一部分に限って適用される場合もある。概念の適用範囲が外延全体に及ぶ場合、その概念は「周延」または「周延されている」という。そして概念の適用範囲が外延の一部だけに及ぶ場合、その概念は「不周延」または「周延されていない」という。
この周延・不周延は判断において、主概念と賓概念の関係を知るのに重要である。判断にはS(主概念)とP(賓概念)が共に周延してもよい場合があるが、SとPが共に周延してはならない場合もあり、またSとPのうちの一方だけが周延すべき場合もあるからである。
例えば「すべての人間(S)は動物(P)である」において、Sは周延、Pは不周延である。これは「全称肯定判断」(A)の主賓関係である(図10—3)。
「すべての鳥(S)は哺乳動物(P)ではない」という判断においては、主概念と賓概念が共に周 延されている。これは、「全称否定判断」(E)の主賓関係である(図10—4)。
「ある花(S)は赤い(P)」において、Sは不周延、Pも不周延である。これは、特称肯定判断(I)の主賓関係である(図10—5)。
「ある鳥(S)は肉食動物(P)ではない」という判断において、Sの一部(主概念の外延の一部)がP(賓概念)の範囲外にあることを表している。つまりSは不周延であり、Pは周延している。これは、特称否定判断(O)の主賓関係である(図10—6)。
以上のAEIOの判断において、主概念と賓概念の周延・不周延の関係はそのまま規則となっており、この規則を離れたらその判断は誤謬に陥る。例えば「すべての仁者は好山家である」という判断から「すべての好山家は仁者である」という判断を導き出したとしたら、不当周延の虚偽に陥るために、その判断は誤りである。全称肯定判断においてSは周延、Pは不周延であるにもかかわらず、結論の判断ではSもPも周延されているからである。
(4) 推 理
推理(inference)とは、既知の判断を根拠にして新しい判断を導く思考をいう。つまり既知の判断を理由にして、「ゆえに……である」という「結論」(conclusion)を導き出すことを推理という。そのとき、すでに知られている判断を「前提」(premise )という。推理において、前提となる判断が一つだけある場合と、二つ以上ある場合があるが、前者を「直接推理」(direct inference)、後者を「間接推理」(indirect inference)という。間接推理には三段論法、帰納推理、類比推理などがある。ここでは間接推理のそれぞれについて簡単に紹介する。
演繹推理(演繹法)
間接推理は、二つ以上の前提から結論を導くものである。また普遍的、一般的原理をもつ前提から特殊な内容の結論を導く推理を演繹推理(演繹法)という。演繹推理の代表的なものが、二つの前提から結論を導き出す間接推理としての三段論法である。
三段論法(定言的三段論法)において二つの前提があるが、初めの前提を大前提といい、次の前提を小前提という。そして大前提には大概念(P)と中概念(M)が、小前提には小概念(S)と中概念(M)が含まれるのであり、結論には小概念(S)と大概念(P)が含まれるようになる。ここで中概念(M)を媒概念ともいう。例えば次のようになる。
大前提:すべての人間(M)は死すべきものである(P)。
小前提:すべての英雄(S)は人間(M)である。
結 論:ゆえに、すべての英雄(S)は死すべきものである(P)。
これを符号だけで表示すれば次のようになる。
MはPである
SはMである
ゆえに、SはPである
この三段論法において大概念(P)の外延が最も大きく、中概念(M)がその次に大きく、小概念(S)の外延が最も狭い。これを図で表示すれば、図10—7のようになる。
帰納推理(帰納法)
間接推理において、二つ以上の前提が特殊な事実を包含する場合、その特殊な内容からより普遍的な真理を結論として導こうとする推理または方法を「帰納推理」(inductive inference)または帰納法という。例を挙げれば、次のようになる。
馬、犬、鶏、牛は死ぬものである。
馬、犬、鶏、牛は動物である。
ゆえに、すべての動物は死ぬものである。
ところでこの帰納推理の結論(「ゆえにすべての動物は死ぬ」)は、判断形式から見ると正しいものであろうか。この結論は「全称肯定判断」である。したがって、動物の概念は周 延しなければならない。ところがこの帰納法では不周延である。馬、犬、鶏、牛だけでは動物の一部だからである。図10—3のように全称肯定判断でなければならないにもかかわらず、図10—5のように特称肯定判断からなっている。
つまり判断形式から見れば、この間接推理は誤っている。しかし、自然界には少数の観察から全体の性質を認識可能ならしめる「斉一性の原理」が働いている。また、自然界に働いている「因果律」が、同一原因から同一結果の想定を可能ならしめている。したがって、帰納推理は大体において正当であることが体験によって証明されているのである。
類比推理(類推)
推理において、また一つ重要なのが類比推理である。今ここに、AとBという二つの観察の対象があるとしよう。そして観察によって、AとBが共に共通な性質、例えばa、b、c、dの性質をもつことが分かっており、Aには、Bにない、もう一つの性質eがあることが分かったとしよう。そしてBはそれ以上詳しく観察しにくい条件下にあるとする。そのとき観察者は、A、Bがa、b、c、dの性質を共通にもっているという事実を根拠として、Aがもっているeの性質を、Bももっているであろうと推理できる。このような推理を「類比推理」または簡単に「類推」という。
例を挙げれば、地球と火星を比較して火星にも地球と同じような生物がいるだろうと推理することがそれである。例えば、両者が次のような共通な性質をもっているとする。
a.両者共に惑星であり、自転しながら太陽の周りを公転している。
b.大気をもっている。
c.ほとんど同じような気温をもっている。
d.四季の変化があり、水もある。
そうすると、これらの事実を根拠として、地球には生物がいるから火星にも生物がいるであろうと推理することができる。これが、すなわち類推である。
ところでこの類推は、われわれの日常生活において、しばしば使われる推理である。今日の発達した科学的知識も、初期には、この類推によって得られたものが多かった。そればかりでなく、日常の家庭生活、団体生活、学校生活、企業生活、創作活動などにおいて、類推は重要な役割を果たしている。したがって、ここに類推の正確性が必要になってくる。その正確性の必要条件は、次のようである。
① 比較される事物に類似点がなるべく多くあること。
② その類似点は偶然的ではなく、本質的であること。
③ 両者の類似点に対して両立しえない性質があってはならない。
以上で、類推に関する説明を終える。形式論理学には、このほかにも、直接推理、仮言的三段論法、選言的三段論法、誤謬論など扱うべき項目がまだあるが、ここでは、ただ形式論理学の要点だけを紹介するのが目的であるから、この程度で終えることにする。