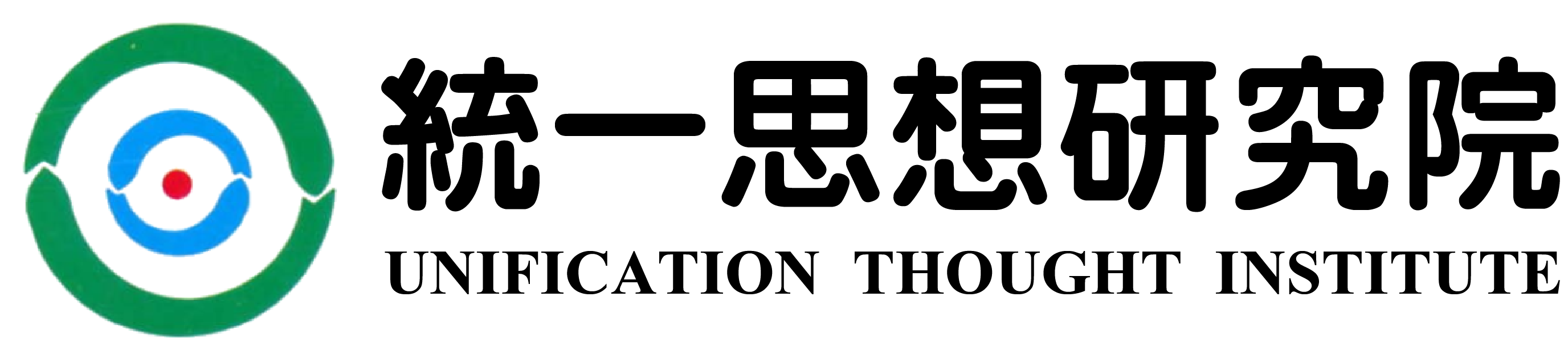(二) ヘーゲル論理学
ヘーゲル論理学の特徴
ヘーゲル論理学の特徴は、「思考の法則と形式」に関する理論ではなく「思考の発展の法則と形式」に関する理論であるという点にある。しかもその思考は、人間の思考ではなく、神の思考である。したがってヘーゲル論理学は、「神の思考がいかなる法則や形式によって発展したのか」を研究する学問である。
この神の思考は、神自体に関する思考から、一定の法則に従って自然に関する思考に発展し、ついで歴史に関する思考、国家に関する思考に発展し、ついに芸術、宗教、哲学に関する思考にまで発展する。このような思考の発展に関する法則と形式が、まさにヘーゲル論理学の特徴である。
ヘーゲル自ら述べているように、ヘーゲル論理学は世界創造以前の神の思考の展開を取り扱っており、「天上の論理」すなわち「創造以前の永遠な本質の中にある叙述」である(2)。しかし、それは形式論理学のように、単に形式的な思考の法則を取り扱うのではない。神の思考の展開であるとしながらも、現実的なものの最も普遍的な諸規定、諸法則を取り扱おうとするものである。
ヘーゲル論理学の骨格
ヘーゲル論理学は「有論」、「本質論」、「概念論」の三部門から成っており、この三部門はまたおのおの細分化されている。すなわち「有論」は「質」、「量」、「質量」から成り、「本質論」は「本質」、「現象」、「現実性」から成り、「概念論」は「主観的概念」、「客観的概念」、「理念」から成っている。そして、これらはまたおのおの細分化されている。例えば「有論」の「質」は「有」、「定有」、「向自有」から成り、さらに「有」は「有」、「無」、「成」から成っているのである。
ヘーゲル論理学において論理展開の出発点となっているのが、有—無—成の弁証法である。この三段階を通過して「有」が「定有」に移行する。そして「定有」にまた三段階があって、それを通過すれば「定有」は「向自有」に移行する。「向自有」にまた三段階があって、これを通過すると「質」が「量」へ移る。「量」が三段階を通過して「質量」に移り、「質量」が再び三段階を通過すれば、「有」に関する理論が終わる。
次は、「本質」に関する理論であるが、「本質」から「現象」へ、「現象」から「現実性」へと移行する。次は、「概念」に関する理論となる。概念は、「主観的概念」から「客観的概念」へ、「客観的概念」から「理念」へと移行する。「理念」の中では、「生命」、「認識」、「絶対理念」という三つの段階がある。そのようにして、「絶対理念」が論理の発展における最後の到達点となっている。
次に、論理の世界すなわち理念の世界は、真に自己を実現するために、かえって自己を否定して自然の領域に移行する。ヘーゲルはこれを「理念自身の他なるものへ移りゆく」といい、自然は「理念の自己疎外、自己否定」(Selbstentfremdung, Selbstverneinung derldee)、または他在の形式(die Form des Andersseins)における理念であるという。自然界においては、「力学」、「物理学」、「生物学」の三段階を通過する。
このように、自己を否定して自ら外に現れ自然界となった理念は、その否定をさらに否定して本来の自己に戻るという。人間を通じて自己を回復した理念が精神である。精神は「主観的精神」、「客観的精神」、「絶対精神」の三段階を通過するが、ここに「絶対精神」が精神の発展の最後の段階である。そこにおいて「絶対精神」は「芸術」、「宗教」、「哲学」の三段階を通過してついに本来の自己(絶対理念)を復帰するのである。ヘーゲルの体系を図示すれば、図10—8のようになる。
有—無—成の弁証法
ヘーゲル論理学においては、有から出発して絶対理念に至るまでを扱っているが、有は有論において扱われており、有—無—成の弁証法から始まっている。したがってヘーゲル論理学の性格を理解するためには、有—無—成の弁証法について調べてみる必要がある。この部分がヘーゲル論理学(弁証法)の出発点であると同時に核心となっているからである。
ヘーゲルの論理学は、有から始まる(3)。有とは、単に「ある」ということであるが、それは最も抽象的な概念であり、全く無規定性な空虚な思考である。ゆえにそれは否定的なもの、すなわち「無」であるという。ヘーゲルにおいては、有と無は共に空虚な概念であり、両者にはほとんど区別がない(4)。
次にヘーゲルは、有と無の統一が成であるという。そこにおいて、有も無も、共に空虚で抽象的であるが、両者は対立の状態において統一をなしたのちに、最初の具体的な思考としての成となる(5)。この有—無—成の論理を基本として、普通ヘーゲルの方法と考えられている、正—反—合、肯定—否定—否定の否定、定立—反定立—総合の弁証法的論理が成立しているのである。
定有への移行
次は、「定有」について述べる。定有とは、一定の形態をもつ有、具体的に考察された有であり、有が単に「ある」を意味しているのに対して、定有は「何ものかである」ことを意味している。有—無—成から定有への移行は、要するに抽象的なものから具体的なものへの移行を意味しているのである。成はそのうちに有と無の矛盾を含んでいるが、この矛盾によって、成は自己を止揚して、つまり一層高められて、定有となるのである。
このように定有とは、特定の有、規定された有である。ヘーゲルはこの定有の規定性のことを「質」と呼んだ。しかしいくら特定されるといっても、ここで考察されているのは、単純な規定性のことであり、規定性一般にすぎない。
有を定有とする規定性は、一方では「或るものである」という肯定的な内容であると同時に、他方では限られたもの、すなわち制限を意味している。したがって、或るものを或るものとする質は、「或るものである」という肯定面から見れば、実在性であり、限られたもの、他のものでないという面から見れば、否定性である。したがって定有においては、実在性と否定性の統一、肯定と否定の統一がなされている。次に、定有は向自有へと移行する。向自有とは、他のものと連関せず、また他のものへ変化せず、どこまでも自分自身にとどまっている有のことである。
有—本質—概念
ヘーゲルが「有論」において論じたのは、「あるということ」はどういうことかということから始まって、変化の論理、生成消滅の論理に関することであった。次に「有論」は「本質論」へと移るが、そこでは、事物のうちにある不変なもの(本質)、および事物の相互関連性が論じられている。次に「有論」と「本質論」の統一としての「概念論」へと移る。そこでは、他者に変化しながら自己であることをやめない事物のあり方、すなわち自己発展が考察されている。この発展の原動力をなすものが、概念であり、生命である。
なぜ神の思考が有—本質—概念というように進んだといえるのであろうか。それは、事物を外側から内側へと関心を移していく人間の認識の過程を見れば分かるという。例えば、ある花を認識する場合、まず外的に現象的に花の存在をとらえたのちに花の内的な本質を理解する。そして、花の存在と花の本質が一つになった花の概念を得るようになるというのである。
論理—自然—精神
すでに述べたように、ヘーゲルによれば、自然とは他在の形式における理念、自己疎外した理念である。したがって論理学を「正」とすれば、自然哲学は「反」となる。次に、理念は人間を通じて再び意識と自由を回復するが、それがすなわち精神である。したがって、精神哲学は「合」となる。
自然界も、正—反—合の弁証法的発展をしているが、それが力学、物理学、生物学の三段階である。しかし、それは自然界そのものが発展する過程ではなくて、自然界の背後にある理念が現れていく過程である。まず力の概念が、次に物理的現象の概念が、その次に生物の概念が現れるというのである。
そしてついに人間が現れ、人間を通じて精神が発展する。それがすなわち主観的精神、客観的精神、絶対精神の三段階の発展である。主観的精神とは、人間個人の精神のことであるが、客観的精神とは個体を越えて社会化された精神、対象化された精神をいう。
客観的精神には、法、道徳、倫理の三段階がある。法とは、国家における憲法のように整備されたものではなく、集団としての人間関係における初歩的な形式をいう。次に、人間は他人の権利を尊重して、道徳的生活をするようになる。しかしそこには、まだ多分に主観的な面(個人的な面)がある。そこで、すべての人が共通に守るべき規範として倫理が現れる。
倫理の第一の段階は、家庭である。家庭では愛によって家族が互いに結ばれており、自由が生かされている。第二の段階は、市民社会である。ところが市民社会に至ると、個人の利害が互いに対立し、自由は拘束されるようになる。そこで第三の段階として、家庭と市民社会を総合する国家が現れるようになる。ヘーゲルは、国家を通じて理念が完全に自己を実現すると考えた。理念の実現した国家が理性国家である。そこでは、人間の自由が完全に実現される。
最後に現れるのが絶対精神であるが、絶対精神は芸術、宗教、哲学の三段階を通じて自らを展開する。そして哲学に至って理念は完全に自己を回復する。このようにして理念は、弁証法的運動を通じて原点に帰る。すなわち自然、人間、国家、芸術、宗教、哲学などの段階を通過して、ついに最初の完全なる絶対理念(神)に帰る。この帰還がなされることによって発展の全過程が終わる(図10—9(6))。
ヘーゲル論理学のトリアーデ構造
すでに説明したように、ヘーゲル弁証法の始まりは有—無—成というトリアーデ(三段階過程)であり、この三段階は矛盾による正—反—合の三段階である。このようなトリアーデがレベルを高めながら反復することによって、論理学—自然哲学—精神哲学という最高のトリアーデを形成するのである。
論理学を構成する三段階過程は有—本質—概念であるが、この概念の段階において絶対精神(神の思考)は理念つまり絶対理念となる。ところで絶対精神は、論理学の段階を通過して、絶対理念となって外部に現れたのち、自然界となり(自然哲学)、さらに人間を通じて主観的精神—客観的精神—絶対的精神となる。そして一番最後には、最初に出発した自己自身、すなわち絶対理念に戻る。
自然哲学や精神哲学は、論理学とは全く別の分野のように考えがちであるが、そうではない。論理学は、三段階過程の初めの段階であるが、その中に自然哲学や精神哲学の原型がすべて含まれているのである。
すでに述べたように、絶対精神は有—本質—概念というトリアーデの概念の段階において理念となるのであるが、この理念は自然哲学と精神哲学の内容のすべての原型となっている。それはいわば、宇宙の設計図をもっている精神である。つまり自然哲学や精神哲学は、この理念の中の原型がそのまま外部に現れた映像にすぎないのである。あたかも映画のフィルムの画像が、スクーリーンに映ったものが映画であるのと同じである。言い換えればヘーゲルの論理学は最高のトリアーデの初期段階であり、自然哲学や精神哲学の原型であって、それらをすべて包含しているのである。それゆえ、論理学においてヘーゲルの哲学体系全体を扱っているのである。絶対精神の発展を扱う、このようなヘーゲルの弁証法は普通、観念弁証法と呼ばれている。
ヘーゲル弁証法の円環性と法則と形式
すでに述べたように、ヘーゲル弁証法は、正—反—合の三段階の発展の反復を通じて高い水準において元の位置に戻ってくる復帰性の運動であり、円環性の運動である。これは低いレベルのトリアーデにおいても、高いレベルのトリアーデにおいても、同じなのである。ところでヘーゲル弁証法のもう一つの特徴は、発展運動が円環性(復帰性)であると同時に完結性であるということである。絶対精神が自己内復帰を終えれば、それ以上の発展はなくなるからである。
ここで、ヘーゲル論理学における法則と形式について述べる。形式論理学における法則は、同一律、矛盾律などであった。そして形式は、判断形式や推理形式であった。ところでヘーゲル論理学の法則は、弁証法の内容である「矛盾の法則」、「量から質への転化の法則」、「否定の否定の法則」などであり、形式は、弁証法の発展形式である正—反—合の三段階過程による発展形式を意味する。このような三段階発展の形式を扱う論理学は普通、弁証法的論理学と呼ばれている。