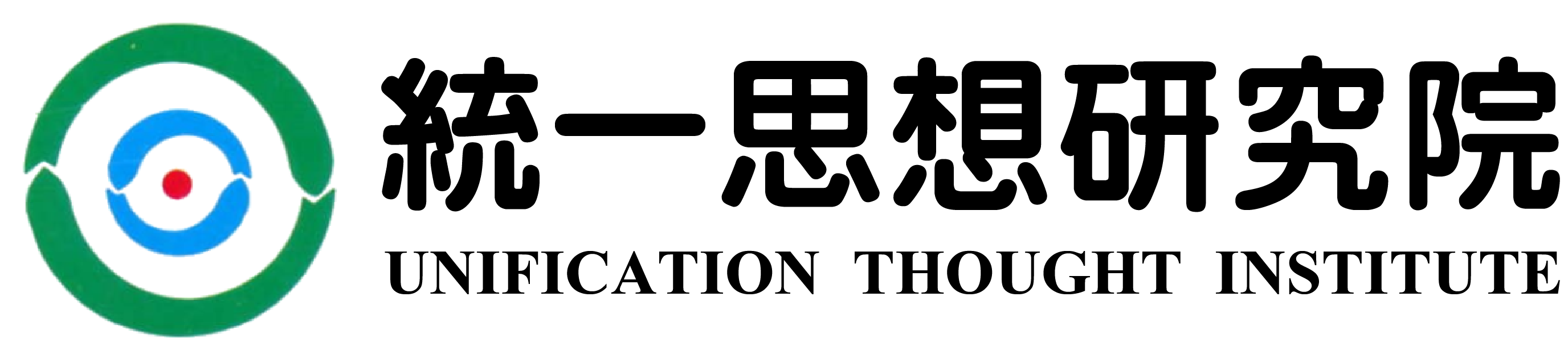三 統一論理学から見た従来の論理学
形式論理学
形式論理学そのものに対しては、統一論理学は何も反対することはない。すなわち、形式論理学の扱っている思考の法則や形式に関する理論はそのまま認めるのである。しかし、人間の思考には、形式の側面だけでなく内容の側面もある。また思考には、理由や目的や方向性があり、ほかの分野との関連性もある。すなわち思考は、思考のための思考ではなく、認識や実践(主管)のための思考であり、創造目的実現のための思考である。つまり、思考の法則や形式は思考が成立し、維持されるために必要な条件にすぎないのである。
ヘーゲル論理学
ヘーゲルの論理学は、神がいかにして宇宙を創造されたのかを哲学的に説明しようとしたものである。ヘーゲルは、神をロゴスまたは概念として理解し、概念が宇宙創造の出発点であると考えた。
ヘーゲルはまず、概念の世界における「有—無—成」の展開について説明した。有はそのままでは発展がないから、有に対立するものとして無を考えた。そして有と無の対立の統一として成が生じるとした。しかし、そこには問題がある。ヘーゲルにおいて本来、無は有の解釈つまり有の意味にすぎないのであって、有と無が分かれているのではない(13)。ところがヘーゲルは、有と無を分けてしまい、あたかも有と無が対立しているかのように説明したのである。したがってヘーゲル哲学は、出発点からすでに誤謬があったのである。
次に問題になるのは、概念が自己発展するという点である。統一思想から見れば、原相の構造において、概念は内的形状に属するのであり、目的を中心として、内的性相である知情意の機能 ——特に知の機能の中の理性——が内的形状に作用することによって、ロゴス(構想)が形成され、それが新しい概念になるのである。したがってロゴスや概念は、神の心の中に授受作用によって形成されるもの(新生体)であって、それ自体が自己発展するということはありえないのである。テュービンゲン大学総長リューメリンは、ヘーゲルの主張する「概念の自己発展」を批判して、次のように述べている。
ヘーゲルのいわゆる思弁的方法なるものが、その創始者ヘーゲルにとって、一体どんな意味をもっていたかということを理解するために……われわれがどんなに骨を折り頭を悩ましたかは言語に絶する。人々はみな他を顧みて頭をふりながら、こう尋ねたものである。一体君には分かるかね。君が何もしないのに概念は君の頭の中でひとりでに動くかね、と。そうだと答えられるような人は、思弁的な頭脳の持主だと言われた。こういう人とは別なわれわれは、有限な悟性的カテゴリーにおける思考の段階に立っているにすぎなかった。……われわれは、なぜこの方法を十分に理解しなかったかという理由を、われわれ自身の天分の愚かさに求めて、あえてこの方法そのものの不明晰や欠陥にあると考えるだけの勇気がなかったのである(14)。
またヘーゲルの弁証法からは、次のような問題が生じる。ヘーゲルは、自然を理念の自己疎外または他在形式であると見た。これは原相論で指摘したように、汎神論——自然を神そのものの現れと見て、両者に区別をおかない見方——に通じる考え方であった。それは、容易に唯物論に転化する素地となったのである。
ヘーゲルの弁証法において、自然は人間が発生するまでの中間的過程にすぎなかった。建物が出来上がると、途中に組み立てられていた足場は取り去られる。それと同じように、人間が発生してからの自然は、それ自体としては哲学的には無意味なものとなったのである。
彼はまた、歴史の発展において、人間は理性の詭計に操られているとしたが、そのために人間は、あたかも絶対精神によって操られる人形のような存在となってしまった。しかし統一思想から見れば、神が一方的に歴史を動かしているのではない。人間の責任分担と神の責任分担が合わさって歴史はつくられたのである。
さらにヘーゲルの正反合の弁証法は円環性であり、帰還性であるので、最終的には完結点に達するようになる。したがってヘーゲルにおいて、プロシアは歴史の終わりに完結点として現れる理性国家とならなければならなかった。しかし、実際は、プロシアは理性国家になれず歴史の中に消えていった。したがって、プロシアの終わりとともに、ヘーゲル哲学も終わりを告げたということになる。
以上のように、ヘーゲル哲学は多くの問題点を抱えていたが、そのような誤りを生じた原因は、彼の論理学にあったと見ざるをえない。そのことを次に検討してみよう。
ヘーゲルは、概念の発展を正反合の弁証法的発展としてとらえた。概念(理念)は自己を疎外して自然となり、その後、人間を通じて精神となり、本来の自身を回復するという。ハンス・ライゼガングによれば、このようなヘーゲルの思考方式は彼の聖書研究に基づいた特有の方式であるという。すなわち、高い総合のうちに止揚されるヘーゲルの対立の哲学は、「一粒の種が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかし、もし死んだら豊かに実を結ぶようになる」、「私はよみがえりであり命である。わたしを信じる者は、たとえ死んでも生きる」というヨハネ福音書をテーマにしたものだという(15)。
そのような立場からヘーゲルは、神をロゴスまたは概念としてとらえ、そしてそのような神が、あたかも地に蒔かれた種の生命が外部に自己を現すように、自己を外部の世界に疎外したと見たのである。そこにヘーゲルの犯した誤りの根本原因があった。
統一思想から見れば、神は心情(愛)の神であり、愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動によって、創造目的を立て、ロゴスでもって宇宙を創造されたのである。その時のロゴスは神の心の中に形成された創造の構想であるだけで、神そのものではない。しかし、ヘーゲルの概念弁証法において、神には心情(愛)や創造目的は見あたらないだけでなく、神は創造の神ではなくて、発芽して成長する一種の生命体であったのである。
ここで、ヘーゲル論理学と統一論理学の重要な概念を比較してみれば、その意味するところは異なっているが、互いに相応する関係にあることが分かる。ヘーゲルにおけるロゴスは、統一思想では神の構想に相当する。ヘーゲルのロゴスの弁証法は、統一思想では原相の授受作用に対応する。そしてヘーゲルの正反合の形式は、統一思想の正分合の形式に対応する。ヘーゲルの帰還的、完結的な弁証法は、統一思想では、自然界においては創造目的を中心とした授受作用による螺旋形の発展運動に相当し、歴史においては再創造と復帰の法則に相当する。ヘーゲルは自然を通じて理念を見いだそうとしたが、統一思想は万物を通じて象徴的に、原相(神相と神性)を発見するのである。したがってヘーゲルの汎神論的性格は、統一思想においては汎神相論——すべての被造物において神相が現れているという見方——をもって克服することができる。
マルクス主義論理学
先に述べたように、旧ソ連の思想界において引き起こされた言語学論争を収拾するために、スターリンは「マルクス主義と言語学の諸問題」という論文を発表し、そこで彼は、言語は上部構造に属するものではなく、階級的なものでもないと結論を下したのであった。その結果、形式論理学の矛盾律・同一律は認められるようになったのである。
しかし、形式論理学の同一律・矛盾律は思考の法則であるだけで、客観世界の発展法則ではなかった。したがって思考が同一律・矛盾律に従うことは認めるとしても、客観世界に関する限り、発展は矛盾の法則(対立物の統一と闘争の法則)に従うというのである。形式論理学は自然界を扱うのではなく、思考を扱うからだというのである。しかしそうすると、「思考は客観世界の反映である」という唯物弁証法の本来の主張が崩れるというアポリア(aporia)が生じてしまったのである(16)。
そのようにスターリンの論文が発表されたあとは、唯物弁証法において、客観世界の法則(矛盾の法則)と思考の法則(同一律)が相反するようになってしまった。それに対して、客観世界においても、思考においても、発展性(変化性)と不変性が統一されていると見るのが、統一思想の主張である。
悟性的段階の思考(あるいは認識)は、主として自己同一的である。なぜならば、外界から来た感性的内容と内部の原型が照合することによって、認識がいったん完了するからである。ところが理性的段階における思考は、発展的になる。しかしそうであっても思考は、段階的に発展するから、それぞれの段階において完結的な(すなわち自己同一的な)側面もあるのである。したがって統一思想は同一律・矛盾律も当然認める立場である。
ともかく唯物弁証法において、形式論理学すなわち同一律・矛盾律を認めるようになったということは、何を意味するのであろうか。本来、唯物弁証法の基本的な主張は、事物を不断に変化し、発展するものとしてとらえるということであった。ところが同一律・矛盾律を認めたということは、たとえ思考に関することであるにせよ、不変性を肯定するようになって、唯物弁証法の変質をもたらしたことを意味するのである。これは、弁証法の修正ないしは崩壊を意味するものである。同時に、事物を自己同一性と発展性の統一として把握する統一思想の主張が正しいことを証明するものである。
記号論理学
思考の正確さや厳密さを期するということは意義あることであって、記号論理学に反対する理由はなにもない。しかし、数学的厳密さだけでは、人間の思考を十分にとらえることはできない。
原相において、内的性相と内的形状が授受作用してロゴスが形成されたが、そのとき内的形状は原則と数理を含んでいるので、授受作用を通じて形成されたロゴスも数理性を帯びている。したがって、ロゴスによって創造された万物には数理性が現れる。だから科学者たちは、自然を数学的に研究しているのである。
人間の思考は、ロゴスを基準にしたものである。したがって人間の思考にも当然、数理性があるのである。言い換えれば、思考は数理的正確さに従ってなされるのが望ましい。ここに、記号論理学が思考を数理的に研究する意義が認められるのである。
しかし、そこには留意しなければならない点がある。それは内的性相と内的形状の授受作用において、心情が中心になっているということである。これはロゴス(言)の形成において、心情が理性や数理より上位にあることを意味している。したがって、人間は本来、ロゴス的存在(理性的、法則的存在)であるのみならず、より本質的にはパトス的存在(心情的、感情的存在)である。すなわち、思考にたとえ数学的厳密さがなくても、そこに愛あるいは感情がこもっていれば、発言者の意向が十分に相手に伝えられるのである。
例えば、誰かが火事に出会って「火だ!」と叫ぶとき、これは文法的に見れば、「これが火だ」という意味か、「今、火事が起きた」という意味か、分からない。しかし、差し迫った場合には、助けを求める訴えの感情がそこにこもっていれば、その言葉に文法的な正確さがなくても、その意味はすぐ分かるのである。
人間は本来、ロゴスとパトスの合性体である。ロゴスだけに従うのでは、人間としては半面の価値しかない。理性的だけでは人間性が不足しており、情的な側面を共に備えて初めて完全な人間らしさが出るのである。したがって、あまり正確でない言葉の方が、かえって人間らしいという場合もある。つまり人間の思考には、厳密を要する面もあるが、必ずしも常に正確に、論理的に表現しなくてはならないと主張することはできないのである。
イエスの言葉を見ても、非論理的な面がたくさん見られる。しかし、その言葉はなぜ偉大なのであろうか。それはその言葉のうちに、神の愛が含まれているからである。したがって、人間の言葉が正確に論理に従っていなくても、その中にパトス的な要素が適切に含まれているとすれば、その意味するところを十分に相手に伝えることができるのである。
先験的論理学
カントは、対象からの感性的内容と人間悟性の先天的な思惟形式が結合して、認識の対象が構成されることによって、初めて認識と思考がなされると主張した。しかし統一思想から見れば、認識の対象には内容(感性的内容)だけでなく形式(存在形式)もあり、認識主体にも形式(思惟形式)だけでなく内容(内容像)もあるのである。カントのいう先天的な形式と感性的内容だけでは、対象に対する思考の真理性は保証されない。それに対して統一思想では、人間と万物の必然的関係から思考の内容と形式と、客観世界の内容と形式の対応性が導かれ、対象に対する思考の真理性が保証されているのである。
統一論理学と従来の論理学の比較
最後に、統一論理学、形式論理学、弁証法的論理学、先験的論理学を比較して、その特徴を表にまとめれば次のようになる(表10—1)。