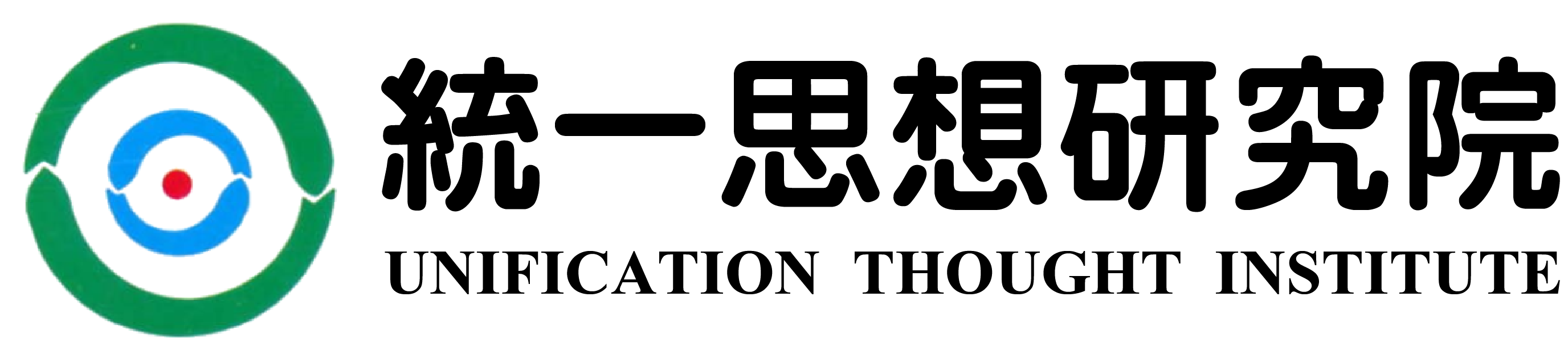一 史的考察
ヘラクレイトスの弁証法(運動法)
ヘーゲルによって弁証法の創始者といわれたヘラクレイトス(Hērakleitos, ca.535-475 B.C. )は、宇宙の根源的な物質(アルケー)を火であると考え、火は絶えず変化しつつあると見た。また「万物は流転する」といって、固定不動のものはなく、一切のものは生成と運動のなかにあると見た。彼は「戦いは万物の父であり、万物の王である」という観点から、万物は対立と闘争によって、生成し、変化していると考えた。そのようにヘラクレイトスが万物を生成、変化、流転という側面から扱ったという点で、ヘーゲルはその方法論を弁証法と呼んだのである。しかしヘラクレイトスは生成、変化の中にも、不変なものがあるといい、それがすなわち法則であって、「ロゴス」と名づけた。また彼は、闘争を通じて調和が生ずるといった。
ヘラクレイトスの方法論は、自然の存在のあり方と自然の発展に関する見方をいうものである。それは事物の動的な側面をとらえようとするものであるから、その方法論(弁証法)を運動法ともいうことができよう。
ゼノンの弁証法(静止法)
万物は流転するというヘラクレイトスの主張とは反対に、エレア学派のパルメニデス(Parmenidēs, ca.515 B.C. 生)は、存在は不生不滅であり、不変不動であるとした。そして、パルメニデスの思想を受け継いだエレアのゼノン(Zēnōn, ca.490-430 B.C. )は、運動を否定し、ただ静止している存在だけがあることを論証しようとした。
物体は動いているように見えても、実は動いていないということを論じた四つの証明があるが、その中の一つが「アキレスは亀を追いこすことができない」というものである。アキレスはトロイ戦争に功労を立てた英雄であって、非常に足が速いが、決して亀を追い越せないというのである。亀が先に出発して、一定の地点にまで進んだとき、アキレスがその後を追いかけたとする。アキレスが亀がいた所に着いたとき、亀はすでにいくらか先に進んでいる。さらにアキレスがそこに着いたとき、亀はすでにさらに少し前に進んでいる。したがって、常に亀はアキレスより先にいるというのである。
もう一つの証明が、「飛ぶ矢は静止している」という飛矢静止論である。A点からC点を目指して飛んでいる矢があるとする。そのとき矢は、AとCの間にある無数の点B1 、B2、B3……を通過する。ところがB1、B2、B3……という点を通過するということは、それらの点で一瞬、止まることを意味する。ところがAとCの距離は無数の点の連続であるから、飛ぶということは静止の連続すなわち静止の永続となる。したがって矢は運動せず、静止しているのである。
ゼノンの方法は、相手の主張を認めるとすれば、その主張にどのような矛盾が生じるかを問答式に問い詰めることによって、相手の主張の誤りを暴露していく論争術であった。
アリストテレスはゼノンを弁証法の創始者と呼んだ。運動を否定して、ただ静止する存在があるということを証明しようとするのがゼノンの弁証法であるから、その弁証法を静止法ともいうことができよう。
ソクラテスの弁証法(対話法)
紀元前五世紀の後半、民主政治が発達したアテネでは、多くの青年たちが政治上の成功すなわち出世のために弁論術を学ぼうとしていた。そこで青年たちに弁論術を教えることを職業とする人々が現れるようになったが、当時彼らはソフィストと呼ばれた。
初期のギリシア哲学は自然を研究の対象と見なしていたが、ソフィストたちは自然哲学から視線を転じて人間の問題を論じた。ところが自然現象は客観性、必然性をもっているのに対して、人間に関する問題はみな相対的であって、主観によって各人の解釈は異なるという相対主義や、その解決をあきらめる懐疑主義が生じてきた。ポリス社会のあちこちを歩き回っていたソフィストたちは、行く場所ごとに価値評価の基準が異なることを目撃し、人間に関する限り、真理は存在しないとまで主張するようになった。そして彼らの教える弁論術は、のちには、いかに相手を論破するかという方法のみを重んじるようになり、そのためには詭弁までもためらわずに用いるようになった。
ソクラテス(Sōkratēs, 470-399 B.C. )は、そのようにソフィストたちが人々を惑わしているのを嘆き、重要なのは、政治的な成功のための技術的な知識ではなくて、真に人間として生きていくための徳であると主張した。そして徳が何であるかを知ることが真の知であるとした。ソクラテスは、真理を得るためには、まず自らの無知なることを知らなくてはいけないとして、「汝自身を知れ」と叫んだ。そして謙虚な心で人と人が対話することによって、真理に到達できると主張した。そのとき、特殊な事柄から出発して一般的な結論に到達するようになるという。
ところで対話を通じて真理に到達するには、まず質問をしてきた相手の魂の中に眠っている真理を対話によって呼び覚まして、それを導き出さなければならないという。ソクラテスはそれを産婆術といった。ソクラテスのこのような真理探求の方法は、弁証法ないし対話法(問答法)といわれている。
プラトンの弁証法(分割法)
プラトン(Platōn, 427-347 B.C. )は、師のソクラテスのいう徳に関する真の知がいかにして成立するかを論じた。そこでプラトンは、事物をして事物たらしめるところの非物質的な存在が先に存在しなくてはならないと主張し、それをイデアまたはエイドスと名づけた。そして多くのイデアの中で善のイデアを最高のものであるとし、人間は善のイデアを直観するとき、最高の生活を送ることができるとした。
プラトンによれば、真に実存するものはイデアであって、感覚界はイデア界の影にすぎない。したがってイデアに関する認識こそ真なる知であり、イデアに関する認識の方法を彼は弁証法と呼んだ。
プラトンの弁証法は、イデアとイデアの関係を決定し、善のイデアを頂点とするイデア世界の構造を明らかにしようとするものであった。イデアの認識には、普遍的な類概念を種概念に分割(分析)していく、上から下への方向と、個別的なものを総合しながら最高の概念を目指す、下から上への方向の二つの方式がある。そのうち総合の方向はソクラテスの弁証法と一致するものであるが、普通、プラトンの弁証法というとき、分割の方法をいう。
ソクラテスの場合、人と人の対話によって真なる知を得ようとするのであるが、プラトンの弁証法は概念の分類の方法であって、思惟が自ら問い、自ら答えていく、思惟自身の自問自答であった。
アリストテレスの演繹法
いかにして正しい知識が得られるかという課題に関する理論を、アリストテレス(Aristotelēs, 384-322 B.C.)は、知識についての学、すなわち論理学として体系化した。「オルガノン」(Organon)としてまとめられている論理学は、正しい思考によって真理に至るための道具であって、それは諸学への予備学であるともいわれている。
アリストテレスによれば、真の知識は論証によるべきである。彼は特殊から普遍に進む帰納法も認めていたが、それは完全性に欠けるとして、普遍から特殊を演繹する演繹法こそ確実な知識を与えるとした。その基本となっている形式が三段論法である。三段論法の代表的な例は、次のようである。
すべての人間は死すべきものである(大前提)。
ソクラテスは人間である(小前提)。
ゆえにソクラテスは死すべきである(結論)。
アリストテレスの論理学は中世において、神学や哲学の諸命題を演繹的に証明するための道具として重要視された。そして約二千年間、アリストテレスの三段論法はほとんど変更なく広く認められてきたのである。
ベーコンの帰納法
中世を通じて超越的な存在としてとらえられていた神は、ルネサンスに至り、次第にその超越的性格を失っていった。そればかりでなく、神を自然の中に内在する存在としてとらえる汎神論的な自然哲学が生じた。そのような中世時代が終わり近世が始まる時期に、一人の哲学者が出現して、自然の探求をいかになすべきかという自然研究の新しい方法を提示した。それがフランシス・ベーコン(Frascis Bacon, 1561-1626 )であった。
ベーコンによれば、過去の学問は「神に身をささげた修道女のように不妊であった」のであり、それは主としてアリストテレスの方法を用いてきたからであると考えた。
アリストテレスの論理学は、論証のための論理学であったが、そのような論理でもっては、他人を説得することはできても、自然現象から新たな真理を導き出すことはできない。そこで新たな真理を見いだす論理として彼が提示したのが帰納法であり、彼はアリストテレスの「オルガノン」に対抗して、自己の論理学を「新オルガノン」(Novum Organum )と名づけた。
アリストテレスの論理学を根拠としている伝統的な学問は、ただ無用な言葉の論争にすぎないとして、ベーコンは、確実な知識を得るためには、まずわれわれが陥りやすい偏見を取り除いて、自然そのものを直接に探求しなくてはならないと主張した。その偏見には四つの偶像(イドラ)がある。種族の偶像、洞窟の偶像、市場の偶像、劇場の偶像がそれである(「認識論」参照)。そのような偶像を取り除いたのちに、純粋な精神でもって、自然に対して実験と観察を行い、そこから個々の現象の中に潜んでいる共通の本質を見いださなければならないのである。
ベーコン以前にも帰納法はあったが、以前の帰納法が少数の観察と実験から一般的な法則を導こうとしたのに対して、ベーコンはできる限り多くの事例を集めること、反証(否定的事例)を重視することなどにより、確実な知識を得ようとするための、真の帰納法を提示しようと試みたのである。
デカルトの方法的懐疑
ルネサンス時代以後、自然科学の目覚ましい成果に基づいて、十七世紀の哲学は機械的自然観を絶対的な真理と考え、これと矛盾しないように努めた。そして機械的自然観をより根源的なものから基礎づけようとしたのが合理論であり、その代表者がデカルト(René Descartes, 1596- 1650 )であった。
デカルトは数学的方法を唯一の真なる学問的方法であると考え、数学におけるように、まずだれにとっても明らかな直観的真理を求め、それを基礎として、新たな確実な真理を演繹的に展開しようとした。
そこで哲学の出発点となる直観的真理をいかにして求めるかということが問題となる。彼は一切の知識の原理となるべき絶対確実な真理を探求するために、疑える限りすべてのことを疑ってみた。そして彼は、一切を疑ってみても、われわれが疑いながら存在しているという、その事実だけは疑いえないということに気づいた。彼はそのことを「われ思う、ゆえにわれあり」(Cogito, ergo sum)という有名な命題で表した。ところで、この命題がなぜ、何の証明も必要ない確実な命題なのかといえば、それは明晰かつ判明であるからだとした。そして、そこから「われが明晰判明に理解するところのものはすべて真である」という一般的な真理の基準を導いた。
デカルトの懐疑は、懐疑のための懐疑ではなくて、確実な真理を発見するための懐疑であって、これを「方法的懐疑」という。デカルトは明晰判明に直観される公理から出発して、個々の命題を証明していく数学的方法に倣って、確実な知識を得ようとしたのである。
ヒュームの経験論
デカルトを代表とする合理論に対して、精神的なものを、経験的に得られる自然法則に基づいて説明していこうという立場をとったのが、イギリスを中心として発展した経験論であった。
ヒューム(David Hume, 1711-76 )は「諸学の完全な体系」を見いだすために、「真理を確立するための新たな方法」により、心的現象を客観的に分析した。そしてヒュームは、心的世界の不変なる自然的な法則を見いだすことによって、われわれの心に関係するあらゆる世界、つまり諸学の根底を明らかにしようとしたのである。
ヒュームは心的世界の要素である観念を分析した。彼は類似、接近、因果性という連合作用によって、単純観念から複合観念が生じると考えた。そのうち観念の類似と観念の接近は確実な認識であるが、因果性は主観的な信念にすぎないとした。
その結果、ヒュームの経験論は、のちに経験と観察による帰納的推理からは客観的な知識は得られないという懐疑主義に陥った。そして一切の形而上学を否定したのはもとより、自然科学すら確実でないと考えるに至ったのである。
カントの先験的方法
合理主義哲学と自然科学の立場から出発したカント(Immanuel Kant, 1724-1804 )は、「ヒュームが独断のまどろみから私をゆりうごかした(1)」といっているように、ヒュームの因果性概念の批判を契機として、因果性の概念がいかにして客観的妥当性をもちうるかを問題にせざるをえなくなった(2)。ヒュームがいうように、因果性の概念が主観的な信念にとどまるものならば、因果律は当然、客観的妥当性を失い、したがって因果律を中心に立てられている自然科学は、客観的妥当性をもつ真理の体系ではなくなるからである。
そこでカントは、いかにして経験一般は可能であるかということ、客観的真理性はいかにして得られるかを問題とした。そのことを明らかにしようとするのが彼の先験的(transzendental )な方法である。
認識がすべて経験的なものであれば、ヒュームのいうように、われわれは決して客観的真理に到達できない。そこで客観的真理性はいかに得られるかを追究したカントは、人間の理性を批判的に検討することにより、われわれの主観の中に先天的(アプリオリ)な要素ないし形式が存在するということを発見した。すなわちカントは一切の経験に先立って、すべての人間に共通な、先天的な形式が存在することを主張したのである。先天的形式とは、時間と空間の直観形式と、純粋悟性概念(カテゴリー)であった。そして対象をあるがままの姿において把握することによって認識が成り立つのではなくて、主観の先天的形式によって、認識の対象は構成されるものであるとした。
ヘーゲルの概念弁証法
カントの方法はいかにして客観的な真理の認識が可能になるかということを目指したものであったが、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831 )の方法は、認識の発展過程としての弁証法であり、それがそのまま存在の発展論理として展開された。
カントは客観的な真理性を保証するためにアプリオリな概念を見いだしたが、ヘーゲルは、概念はアプリオリでありながら、自己を越えて自己運動すると見た。すなわち概念は概念を直接的に肯定する立場から、その概念とは相反する規定(対立)つまり否定が存在することを知るに至り、そしてこの矛盾する二つの規定を止揚(aufheben )して、総合統一する新しい立場、つまり否定の否定の立場に発展していくのである。
ヘーゲルはこの肯定、否定、否定の否定の三つの段階を、即自(an sich )、対自(für sich )、即自対自(an und für sich )と名づけた。この三段階は正・反・合、または定立・反定立・総合ともいわれている。
ヘーゲルは概念の自己展開の推進力となっているものを「矛盾」であると見た。彼は「矛盾は、あらゆる運動と生命性の根本である。ある物は、それ自身の中に矛盾をもつかぎりにおいてのみ運動するのであり、衝動と活動性をもつのである(3)」と述べた。そのように矛盾を推進力とする自己運動の論理が、ヘーゲルの弁証法の根本を成しているのである。
そしてヘーゲルは、概念は自己発展して理念に至り、概念(理念)は自己を否定し、外化して自然として現れ、さらに人間を通じて精神として発展していくという。したがってヘーゲルの弁証法は概念の発展の方法であると同時に、客観的世界の発展の方法でもあった。
マルクスの唯物弁証法
近代において弁証法を発展させたのはドイツ観念論であり、ヘーゲルがその頂点であった。しかしヘーゲルの弁証法は観念論のために歪められているとして、マルクス(Karl Marx, 1818-83 )はヘーゲルの観念弁証法を逆立ちさせて、唯物論の立場から弁証法を再構成した。エンゲルス(Friedrich Engels, 1820-95)によれば、マルクスの弁証法は「自然、人間社会および思考の一般的な運動・発展法則に関する科学(4)」であるが、自然と社会の発展の方法の基礎になっているだけでなく、思考の発展もそれに基づいたものであるという。
ヘーゲルの観念弁証法もマルクスの唯物弁証法も、共に正反合の三段階の展開過程として理解される矛盾の弁証法である。矛盾とは、一つの要素が他の要素を排斥(否定)しながらも、相互の関係を維持する状態であるが、ヘーゲルの弁証法の場合、矛盾の概念は総合(統一)に重点が置かれているのに対して、マルクスの弁証法における矛盾の概念は、一方が他方を打倒、絶滅させるというような闘争の意味が加えられている。
エンゲルスによれば、唯物弁証法の基本法則は、①量から質への転化の法則、②対立物の統一と闘争の法則(対立物の相互浸透の法則)、③否定の否定の法則、の三つである。
第一の法則は、質的な変化は量的な変化によって起きるが、量的変化がある一定の段階に達するとき、飛躍的に質的変化が起きるという。
第二の法則は、事物の中にある対立物が、一方では互いに相手を必要としながらも、もう一方では互いに排斥し合うなかで、つまり対立物の統一と闘争によって、事物の発展と運動がなされるという。
第三の法則は、事物の発展において、古い段階が否定されることによって新しい段階に移り、それが再び否定されることによって第三の段階に移るが、この第三の段階への移行は、高い次元における初めの段階への復帰であるという(これを「螺旋形の発展」という)。
エンゲルスがこの三つの法則を示す際に、ヘーゲルの「論理学」を参照しているが、第一法則は「有論」で、第二法則は「本質論」で、第三法則は「概念論」で展開されたと見ているのである。
唯物弁証法の三つの法則の中で、最も核心的なものが、第二の「対立物の統一と闘争の法則」である。そこにおいて、対立物の統一と闘争が矛盾の本質であるというが、実際は統一よりも闘争にずっと比重を置いている。事実、レーニンは「対立物の統一(一致・同一性・均衡)は条件的、一時的、経過的、相対的である。たがいに排斥しあう対立物の闘争は、発展、運動が絶対的であるように、絶対的である(5)」といい、さらには「発展は対立物の闘争である(6)」とまでいって、闘争を強調しているのである。
フッサールの現象学的方法
フッサール(Edmund Husserl, 1859-1938 )は一切の諸科学の基礎を実現する基礎学(Grundwissenshaft)すなわち第一哲学として現象学(Phänomenologie )を提唱した。現象学は、諸科学の理論を構成する意識そのもの、認識を遂行する意識そのものを問題としている。デカルトの「われ思う」(コギト)という絶対的確実性を出発点とし、従来の哲学の根底に潜んでいる形而上学的な独断を排しつつ、厳密な学として、意識の本質を考察した。そして一切の先入観を排しながら、純粋意識を直観的に明らかにしようとしたのである。
そのために「事象そのものへ!」(Zu den Sschen selbst! )をモットーとした。ここで事象とは、経験的事実をいうのではなく、一切の先入観を排除した事実そのものをいうのである。フッサールの現象学は、経験的な事実から経験的なものを排除し、本質的な現象を直感する段階を経て、その外界の対象の本質を内在的な本質に転換させたのち、先験的な純粋意識の構造を分析し、記述するものである。
われわれの前に横たわっている自然的世界を、自明なものと見なす日常的な態度を「自然的態度」(Naturliche Einstellung )という。しかし自然的態度には、根深い習慣性や先入観が働いているのであって、自然的態度によって認識される世界は、事象そのものの世界であるとはいえない。そこで「自然的態度」から「現象学的態度」へ移行しなくてはならないが、そのためには「形相的還元」と「先験的還元」という二つの段階を通過しなくてはならない。事実の世界から本質の世界へ移ることを、フッサールは「形相的還元」(eidetische Reduktion )という。そのときなされるのが、「自由変更」(freie Variation )による「本質直観」(ldeation )である。つまり、存在する個々のものを自由な想像によって変化させてみて、それでも変わらない普遍的なものが直観されるとき、それが本質である。例えば花の本質は、バラ、チューリップ、つぼみ、しおれた花などについて検討し、それらにおいて不変なるものを取り出すことによって得られるのである。
次になされるのが「先験的還元」(transzendentale Reduktion )である。それは外界の存在が確実であるか否かということに関して、判断を停止させることによってなされる。それは外界の存在を否定するとか、疑うことではなく、ただ「判断中止」(epochē)あるいは「括弧入れ」(Einklammern )を行うだけである。
そのとき、括弧に入れられないで(排除されないで)、残ったものが「純粋意識」(reines Bewussutsein )あるいは「先験的意識」とされる。そしてその中に現れてくるのが「純粋現象」(reines Phänomen )である。このような純粋現象を把握する態度が現象学的態度である(図11—1)。
純粋意識の一般的構造を研究してみると、純粋意識は志向作用であるノエシスと、志向される対象であるノエマから成り立っていることが分かる。その関係は、考えるものと考えられるものの関係といってよい。このように現象学は純粋意識の内在的本質すなわち純粋現象を忠実に記述しようとしたのである。
分析哲学の言語分析
現代の欧米で哲学の主流の一つになっているのが分析哲学である。分析哲学とは、一般的に言語構造の論理的な分析に哲学の主要な任務があると考える立場である。これを初期の論理実証主義(logical positivism )と、後期の日常言語学派(ordinary language school )の二つの立場に分けることができる。
世界は究極の論理的単位である原子的事実の集まりであるという論理的原子論(logical atomism )を唱えたラッセル(Bertrand Russell, 1872-1970)やヴィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein, 1889-1951 )の影響を受けて、ウィーンの哲学者シュリック(Moritz Schlick, 1882-1936 )やカルナップ(Rudolf Carnap, 1891-1970 )を中心にして形成されたのが論理実証主義(別名ウィーン学派)である。
論理実証主義は、経験的知覚によって検証されるものだけが正しい知識であると主張する。ところで、事実についての研究はすべて科学が行うべきものである。そこで哲学の使命は、言語の論理的分析を通じて、日常の言語表現のもっている曖昧性を取り除くことである。そして従来の言語を捨てて、すべての科学に共通な一つの理想的な人工言語の確立を目指した。それは物理学が用いる数学的言語、物理学言語であって、そのような理想言語によって諸科学の統一を図ろうとした。論理実証主義の旗印は、反形而上学、言語・論理の分析、科学主義であった。
ところが、科学的知識ですら検証されない命題に基づいていること、論理実証主義の主張自体が一つのドグマであることなどが分かり、論理実証主義の限界が現れるようになった。そこで、ムーア(George Edward Moore, 1873-1958 )やライル(Gilbert Ryle, 1900-76 )を中心として日常言語学派が成立することになった。
日常言語学派も、哲学の任務は言語の論理的分析であると考えるが、理想的な人工言語の構成を断念し、日常言語に基づいて概念の意味を明らかにし、論理構造を見いだすことをその任務とした。そのようにして、反形而上学的態度も緩和された。