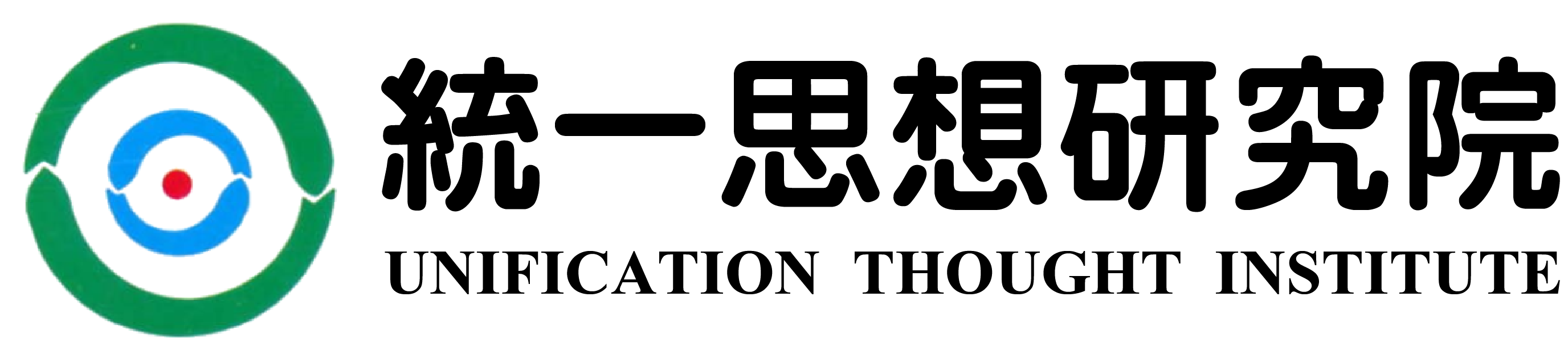三 統一方法論から見た従来の方法論
以上の統一方法論をもって、従来の方法論を評価してみることにする。
ヘラクレイトスの弁証法(運動法)
ヘラクレイトスは、「万物は流転する」といった。彼は、被造世界における発展的な側面のみをとらえ、自己同一的な側面を軽視したか、見逃したといえる。また彼は「闘争は万物の父である」といい、万物の発展の原因を対立物の闘争に求めているが、万物は相対物の調和的な授受作用によって発展するというのが統一方法論の立場である。
ゼノンの弁証法(静止法)
まずゼノンの「飛矢静止論」について考察してみよう。飛んでいる矢がある点で静止しているというとき、その点は空間をもたない数学的な点を意味しているとしかいえないが、矢の実際の運動は時間、空間の中で行われている。物体の運動する速度(v)は空間中の距離(s)を時間(t)で割ったものであり、v=s/tで表される。だから物体の運動は、一定の時間と一定の距離において考えなくてはならない。位置だけあって空間のない点(数学的な点)において、物体の運動を論ずることはできないのである。だから、ある点における物体の運動をいうとき、その点がいかに微小であっても、一定の空間のもとで考えるべきであり、またある瞬間における運動をいうとき、その瞬間がいかに微小であっても、一定の時間において考えなくてはならない。そうすれば、運動している物体は静止することなく、ある点を通過するということがはっきりといえるのである。
この問題に関して唯物弁証法は、物体はある瞬間にある場所にありながら、同時にないと主張して、ゼノンのパラドックスを解決し、運動を説明したという。しかし、これもゼノンと同様に詭弁にすぎない。運動している物体の位置は時間の関数で表されるのであって、「一定の瞬間」には必ず「一定の場所」が一対一に対応している。したがって「ある瞬間」に「ある場所」にあって、同時にないということはありえないのである。
結局、運動している物体は、(1)静止することなく空間を通過しているのであり、(2)ある瞬間に、ある場所に、運動しつつ「ある」のである。
次は「アキレスと亀」であるが、ゼノンは時間を無視して空間のみで議論したから、アキレスが亀を追い越せないという誤った結論に達したのである。一定の時間の経過から見れば、アキレスは確実に亀を追い越すことができるのである。
ゼノンは、すべてのものは不変不動であり、不生不滅であることを論証しようとした。そのために、詭弁までも用いて運動や生滅を否定しようとした。ゼノンはヘラクレイトスとは逆に、事物の発展的側面を無視して自己同一的側面のみをとらえたといえる。
ソクラテスの弁証法(対話法)
ソクラテスは、人と人が謙虚な心でもって対話をすることによって真理に到達できると考えた。これは、人と人の間の外的発展的授受作用による真理の繁殖である。ソクラテスは、人と人との間の正しい授受作用のあり方を説いたのである(図11—4)。
プラトンの弁証法(分割法)
プラトンは、イデアの世界について研究した。原相論において、原相の内的形状にはいろいろな観念や概念があることを明らかにしたが、プラトンはそれらの概念の世界をイデア界としてとらえ、分析と総合の方法によって、イデア界のヒエラルキー構造を明らかにしようとした。概念の分析や総合は、概念と概念を比較することによってなされる。これは、対比型の授受作用であり、人間の心の中で行われるから内的授受作用である。結局、プラトンのイデア論は、対比型の内的授受作用の一側面を説いた理論であった(図11—5)。
アリストテレスの演繹法
アリストテレスの演繹法は、三段論法である。まず普遍的真理を立て、次にそれより限定された真理を述べて、それから結論を出す。先の例で言えば、「すべての人間は死すべきものである」という大前提と、「ソクラテスは人間である」という小前提を対比して、「ソクラテスは死すべきである」という結論を出す。これは、命題と命題の間の対比型の授受作用である。
さらに「ソクラテスは人間である」という命題自体、「ソクラテス」と「人間」を対比して得られるものであるから、これも対比型の授受作用である。したがって、アリストテレスの演繹法は、プラトンの場合と同様、対比型の内的授受作用による真理の追究の方法であるといえる。
ベーコンの帰納法
ベーコンは真理を得るためには、まず偏見(イドラ)を捨てて、実験と観察によらなければならないと主張した。A、B、C……の実験の結果がすべてPであれば、Pという結論を一般的法則として見なすというのが帰納法である。帰納法は、人間と万物(自然)との外的授受作用に基づいて真理を得ようとする立場である。また実験と観察によって得られた多くの事実を対比して結論を得るから、対比型の授受作用である。したがってベーコンの帰納法は、対比型の外的授受作用による真理の追究の方法であるといえる(図11—6)。
デカルトの方法的懐疑
デカルトは一切のものを疑ってみて、その結果、「われ思う、ゆえにわれあり」という確実な第一原理に達したという。ここでデカルトが一切のものを疑ったということは、すべての万物や現象を否定したことを意味し、したがって統一思想から見れば、神の宇宙創造以前の段階にさかのぼるのと同じ立場にあるといえる。その状況において、「われ思う」は宇宙創造直前の神の構想や考えに相当する。
デカルトは「われ思う、ゆえにわれあり」という前に「われはなぜ思うか」を問うべきであった。そうすれば彼の理性論は、のちに彼の後継者によって独断論に陥らなかったはずである。とにかく、この「われ思う、ゆえにわれあり」の自覚は、統一思想から見れば、人間の心の中でなされる内的授受作用は確実な認識であるという意味である。
またデカルトは、上記の第一原理から「われわれが明晰かつ判明に理解するところのものはすべて真である」という一般的な真理の基準を導いたが、これは内的発展的四位基台の形成による真理の繁殖を肯定する命題である(図11—7)。
ヒュームの経験論
ヒュームは因果性を主観的な信念にすぎないとしたが、因果性はヒュームが主張するように主観的なものだけではなくて、主観的であると同時に客観的である。そのことについては、すでに認識論で明らかにしたとおりである。ヒュームはまた、物質的な実体を否定しただけでなく、精神的な実体(自我)をも否定し、存在するものは観念の束にすぎないとした。統一思想から見れば、彼は内的形状(観念)だけを確実なものと見たといえる。ヒュームは心的現象を分析することにより、哲学の完全な体系をつくろうとしたが、ばらばらの印象や観念のみによって、それをなそうとしたところに問題があった。
カントの先験的方法
カントは、対象から来る混沌とした感性的内容が、主観(主体)のもつ先天的形式によって構成されることによって、認識が成立すると主張した。人間主体(主観)と対象の相対関係によって認識が成立するという点では、統一思想も同じである。しかし統一思想から見れば、主体は形式(思惟形式)だけでなく内容(映像)も備えているのであり、両者を合わせて原型という。また対象から来るのは、混沌とした感性的内容ではなくて、存在形式をもった内容である。カントの構成論に対して、統一思想は照合論を主張する。カントの先験的方法に基づいた構成論は、統一思想の授受法に基づいた照合論を、カントの立場から表現したものであると見ることができる。
ヘーゲルの概念弁証法
ヘーゲルは、概念と世界(宇宙)の発展を矛盾の止揚と統一の過程として、あるいは正反合の過程としてとらえた。しかし、統一思想から見れば、矛盾によって発展するのではない。発展は主体と対象の関係にある相対物が、目的を中心として授受作用することによって発展するのであり、その過程は正分合となる。そのとき正は目的を、分は相対物を、合は合性体または繁殖体を意味する。
ヘーゲルのいうように、概念が概念自体の矛盾によってひとりでに発展するのではない。内的性相である知情意の機能が内的形状(観念、概念など)に作用し、新しい概念(思考)を形成しながら思考が発展していくのであり、これはすでに論理学で説明したように、思考の螺旋形の発展に相当する。統一思想の主張する相対物の授受作用による発展を、ヘーゲルは対立する要素の相互作用という立場から誤ってとらえたのである。
マルクスの唯物弁証法
マルクスは、物質的存在のあり方を基礎として精神作用はその反映であるとしたが、統一思想から見れば、性相(精神)と形状(物質)は主体と対象の相対的な関係にあるから、精神的な法則(価値法則)と物質的な法則には対応関係があるのである。
「量から質への転化の法則」に対しては、統一思想は「質と量の均衡的発展の法則」を代案として提示する。量から質へではなく、また量的変化がある一点に達するとき、飛躍的な質的変化が起きるのでもない。質と量の関係は性相と形状の関係であり、質と量は同時的、漸次的、段階的に変化するのである。
「対立物の統一と闘争の法則」に対しては、統一思想は「相対物の授受作用の法則」を代案として提示する。対立物の闘争は破壊と破滅を生じるのみであって、決して発展をもたらさない。すべての事物は、共通目的を中心とした相対物の調和的な授受作用によって発展するのである。
「否定の否定の法則」に対しては、統一思想は「肯定的発展の法則」を代案として提示する。自然や社会は、それを構成している主体と対象の相対的要素が円満な授受作用を行うことによって、肯定的に発展しているのである。そして自然界において、無生物は空間的円環運動を行い、生物は時間的円環運動(螺旋形運動)を行っているのである。
今日までの方法論のなかで、マルクスの唯物弁証法ほど大きな影響力をもったものはなかった。マルクスの提示した弁証法が自然の発展においても有効であることを証明しようとして、エンゲルスは八年間、自然科学を研究した結果、「自然は弁証法の検証である(7)」という結論を下した。しかし今日に至り、唯物弁証法の間違いは明白なものとなった。そして自然現象の内容をよく検討してみれば、自然は「弁証法の検証」ではなく「弁証法の否定」であり、かえって「授受法の検証」であることが明らかになったのである(図11—8)。
フッサールの現象学的方法
フッサールは、まず自然的世界の事物から出発しているが、事物とは、統一思想から見れば、性相と形状の統一体である。そして形相的還元によって本質直観を行うというが、本質は存在者の性相に相当する。さらにフッサールは、判断を中止して意識(純粋意識)を分析して見れば、ノエシスとノエマの構造があるというが、これは統一思想から見れば、性相(心)の内部構造である内的性相と内的形状にそれぞれ対応するのである。フッサールの現象学的方法を統一思想の観点から見れば、図11—9のようになる。
フッサールもデカルトと同様に、無意識のうちに、統一思想の内的四位基台に関する内容を重要視して、その分析によって、学問を統一しようとしたということができる。
分析哲学の言語分析
言語は、内的発展的授受作用によって形成されるが、内的授受作用には理性を中心とした知的な面(ロゴス的側面)と、情感を中心とした情的な面(パトス的側面)がある。分析哲学は、そのうちロゴス的側面だけをとらえて論理性のみを追求したのである。統一思想から見るとき、言語は本来、愛を実現するためのものであって、言語の論理構造は、愛の実現のために必要な一つの条件にすぎないのである。
ところで言語の営みは、思想の形式であり、それは一種の創造活動である。創造活動の中心になっているのは心情である。したがって、愛を中心とする情的な要素が思想形成に際して主体的な役割をなしているのである。ところが、分析哲学は終始一貫して、言語の論理的な分析だけに重きを置くあまり、言語を通じて形成される思想の創造的側面や心情的、価値的側面を無視する結果になったのである。